元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。
公開日:2025年2月21日
「硬派なOUT」というテーマでどうしても外せないのがアニメ・ジュンさん[89]だと思っています。その半分ぐらいはアニメ・ジュンさんの評論から来てるイメージじゃないかなとも思うんです。'79年4月から'87年の12月までおよそ8年、OUTに連載されているんですが、途中でご自分の記事の中でも「全然人気がない」と書かれていて。「どうしたら読者から人気が出るだろうかって何かやってみたけどあまりうまくいかなかった」みたいな節もあります(大徳・苦笑)。アニメ・ジュンさんを起用されたきっかけと、どういうお考えで記事を依頼し続けたのか、ということをお聞かせください
彼はコミックマーケットの創始者の1人なんですよ。アニメ・ジュン(霜月たかなか)と米澤嘉博[90]って漫画評論家と、亜庭じゅん[91]っていう評論家・ライター、この3人でコミックマーケットを立ち上げたんです。
四谷公会堂っていうのが東京の四谷にあった時代のことだけど、コミックマーケットの企画に泊まり込みでファン連中といろいろ語り合ったりするっていう合宿があったんです。コミックマーケットの3回目の時に、そこで知り合って、いろいろ話してるうちに…というのが最初の出会いでした。あのころはまだ漫画評論なんて確立されてませんでしたが、僕から見ると米澤さんも亜庭さんも霜月さんも、漫画という表現をきちんと批評の言葉で残すということをやれている人たちだったんです。
彼らと話をしてみると霜月さんは漫画だけじゃなくてアニメもすごくよく見てるんです。あそこまでアニメをきちんと見込んでる人っていない。だから、漫画に関して書いている批評的・評論的なこと…単純にファンのいい悪いという感想文ではないちゃんとした論理を持った評価を、ぜひアニメーションでもやってほしい、と原稿依頼しました。
その当時、他のアニメ雑誌ではそういう評論的なものはほとんど取り上げてなかったんです。アニメックが一部取り上げてましたけども、あれははっきり言って、もうしわけないけど、やはり感想文なんですよ。アニメ評論といえるようなものではなかった。だけどアニメジャーナリズムってものがもしあるんだとしたら、ファン意識が最初に来るのではなく、きちんとした論理的な評価・客観的な形でアニメーションを評価する、そういうコーナーがあってもいいんじゃないかって僕は思っていた。アニメ評論を載せたかったんです。
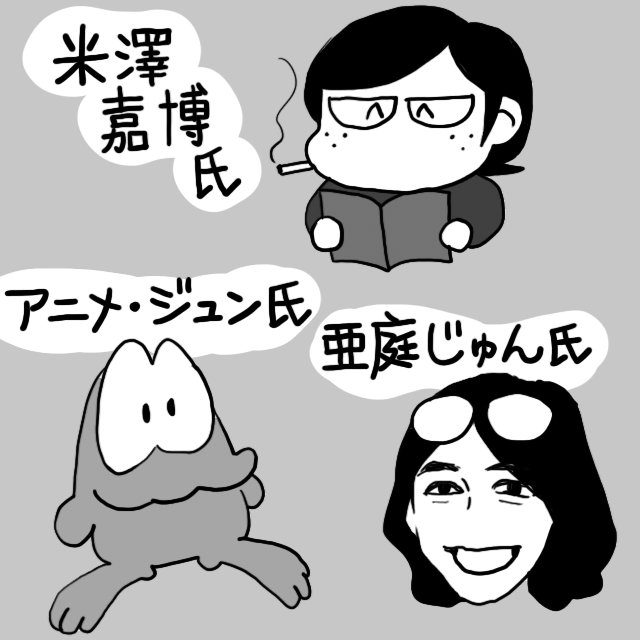
アニメ批評って他にも映画評論家の佐藤忠夫さんとか[92]白井佳夫さんとか[93]、あるいは他の人にも文章を頼んだことはあるんですよ。OUTにも載ってると思います。ただあの人たちは主に実写の映画評論家であって、アニメーションというものはあんまり見てないんですよ。やっぱり基本的には見ててほしいなっていうのはちゃんとあるわけで。
そういう意味で言えば、霜月さんはちゃんとアニメを見てるのでね。ただし
「霜月たかなかって名前でアニメ評論を書くのはやっぱりおかしいだろう、もし書くんだとしたらアニメ・ジュンっていうもう1つのペンネームで書きたい」
って言うから、それならそうしてくれと。で、それに対してこんなこと書けとかあんなこと書けとか、そんなことは一切言わない。あなたの書いた内容に関して僕は、口を出さないですから、お任せしますと。
だからアニメ・ジュンの評を読んで、僕なんかは「あれ、これは違うかな?」ってことはいっぱいあった。でも彼が、漫画の評論もやってアニメをきちんと見ていてそういうふうに評価してるんだから、それに対して編集者がね、気に食わないからここを書き直してほしいとか、載せないよ、っていうことを言うのは、僕は良くないと思うんですよ。
もし気に食わないんだったら、まず話し合って、その上で、載せない・使わないっていう判断はあるんだよ、ちゃんとした議論の果てにね。だけども、そうした事で揉めたことは一度もなかった。アニメ・ジュンさんの意見が100パーセントだとは思ってないけれども、僕の中の許容範囲では載せ続けるべきだって思ってた。読者からは、けっこう反発をいろいろ浴びたけれども載せ続けた。
すごく初期の頃には、『キャプテン・ハーロック』を批判して、それがけしからんっていう読者投稿があったみたいなんですよね[94]。アニメ・ジュンさんも、そういったことに対して時々は「私はこう思ったからこう書きました」って反論されている。でも多くの場合は、批判は批判として受け止めるけど、それをいちいち雑誌に載せるっていうことはしてなかったと思うんです。で、その批判って、読者の側ももちろんあったと思うんですけど、業界もすごかったんじゃないかなと。
たしかに、業界からはけっこうあったよ。ただ作り手っていうのは、それに対して作品以外のことで語るって、おかしいんだよ。やっぱり作品で語るべきなんですよ。だから、自分の作品が批判されてるってことに対して、批判に対する批判を載せるってことを雑誌を使ってやらせろって言ってきた人はひとりもいないですから。富野さんみたいに「批判おおいに結構」って思ってる人の方がむしろ多かった。でも感情的に「なんでこんなこと書くんだ許せねえな」って思っている人はたくさんいたかもしれない。
それで例えば、OUTの取材は受けない、みたいなことは何もなかったんですか。
それはなかったですよね。雑誌の内容が元で「あなたのところの取材に答えません」って言われたことはほとんどないです。「声優って言われるのは嫌だ」って言って取材させてくれなかった人ぐらいはいるけど、ほんの数例ですよ。
アニメ・ジュンさんは、富野さんをはじめ、押井さん・宮崎さんといったビッグネームと対談されていますね。対談の内容もすごく面白いんですけど、そこにアニメジュンさんを起用したのが面白いなと思います。
それは彼のアニメ評論を載せる理由と同じでね。彼は批評する能力も持ってるし、アニメーションもたくさん見ていてかなり知識があるから。ただ、こんなこと言っちゃ悪いけど、彼にはそれをOUTの読者がうまく理解できるように器用に書くことができなかったところがある。でもそこは、本人の文体みたいな形になっちゃってて、何度言ってもなかなか変わらなかったね。
アニメ評論というともうひと方、南田操さんも少し後に連載[95]を持たれています。南田操さんはどこから繋がったんですか。
南田操さんはね、東大の学生だったんだけども、売り込みに来た。アニメ・ジュンの批評ページに対して、「僕はこういう違う意見の持ち主なんだけども、こういうの載せてくれませんか」と言うので、話しているうちに、彼はすごくアニメーションに詳しいし好きだし、ある程度見る力もあるなって思ったから、じゃあいいよ、そういって、それで始めたの。
かなりファン寄りの…ちょっとオタク的で、時たま当時の哲学理論と関連して語ったり理屈っぽくなる部分があったけど、そういう意見も載せていいんじゃないかなって思ったから、南田操さんを載せた。
そのふたつ違ったアニメ評論が載ってるあたりが、硬派なOUTのイメージを作ったと思うんです。もう一人、これは1年ぐらいしかなかったんですけど、米澤嘉博さんがコミックについて評論を書かれています[96]。それもまたすごく面白くて。ネットによると、この連載で「ロリコン」という言葉が商業誌に最初に書かれたということらしいんですが。米澤さんのお話も聞かせてもらってよろしいですか?
今はないんだけど、渋谷に薔薇園という喫茶店があったんです。毎週木曜日の夜にその喫茶店に集まって、漫画について議論しようっていう会があった。その会に僕も何度も行って話してるうちに米澤さんと親しくなって、米澤さんの批評能力とか知識とかそういうものに感心したんです。あ、この人ただの漫画好きじゃないなと。ちゃんと漫画を評価できる力も持ってる、文化批評もできる人だ、って思ったので、じゃあ米澤さん書いてくださいって言って、連載してもらった。すでにその頃、漫画評論家でけっこう米澤さんは多忙だったんですが。
米澤さんはすごい。あれだけきちんと漫画を読み込んでて、ちゃんと客観的に評価できる漫画評論家。いっぱい漫画評論家みたいな人はいるけれども、今でもあの人を超える人いないんじゃないですか。やっぱり米澤さんみたいな人が必要なんじゃないですかね。惜しい人を亡くしちゃったよな。
連載が終わったのは、健康状態とかそういうことですか?
それもある。あんまり丈夫な人じゃなかったんで、とにかくヘビースモーカー。チェーンスモーカーですよ。タバコ吸いすぎ。
米澤さんの連載のちょっと後に、さくまあきらさんが、高橋留美子さんや鳥山明さんと対談されていました[97]。ただ長く続いたというよりは時々あった、みたいな感じで、あんまりアニメよりはコミックの方に力を割いてなかったように見えたんですが、出版社から圧力がかかったとかそういうことはあったんですか。
そういうわけではなくて、漫画の場合は、アニメと比べて力として出版社の割合が大きいんですよ。だから特定の漫画作品を多く取り上げようとしたりすると…アニメはあんまり「それやらないで」という抵抗ってないんだけど、出版社は同業者の部分があるから、どこかでライバルなんですよ。だからなかなかね。例えば小学館や講談社の漫画を大きく特集で取り上げるっていうのは、太鼓持ち的な特集だったらできたかもしれないけども、そうじゃないものに関してはなかなか難しかったですね。
作家を引っ張り出してくることっていうのは非常に難しいんですよ。なぜかというと、作家を他の出版社に引き抜かれちゃうのがいちばん出版社の嫌がることだから。インタビューに出したり取材に出したりすることは出版社にとってはあんまり好ましくない。そもそもそれに耐えられるような作品がどれだけあったのかなって思う部分もありますけどね。
 吾妻ひでおの場合[98]は、漫画家として吾妻さんがそれほど認知されてなかった。だけど、さっき言った米澤さんが勧めたこともあって、この人の漫画面白いよねっていうのがすごくあった。メジャーの出版社にも描いてたけれども、あんまりうるさいところではなかったので、じゃあ大々的に特集しましょうよって言ったら、のってくれたっていうところもあるんだよね。いや、それは本当は高橋留美子とかさ、特集やりたかったなと思いますよ。でもやっぱりなんともね。本人を引っ張り出すぐらいが精一杯(笑)。
吾妻ひでおの場合[98]は、漫画家として吾妻さんがそれほど認知されてなかった。だけど、さっき言った米澤さんが勧めたこともあって、この人の漫画面白いよねっていうのがすごくあった。メジャーの出版社にも描いてたけれども、あんまりうるさいところではなかったので、じゃあ大々的に特集しましょうよって言ったら、のってくれたっていうところもあるんだよね。いや、それは本当は高橋留美子とかさ、特集やりたかったなと思いますよ。でもやっぱりなんともね。本人を引っ張り出すぐらいが精一杯(笑)。
じゃああの対談が実現したのはさくまさんの人脈?
さくまさんのおかげです。ほんとにその通り。
その当時、例えば『ぱふ』[99]とかそういう漫画情報誌がありましたが、OUTはそういうふうになろうとは思わなかったんですか。
『ぱふ』ともう一つ、『COMIC BOX』[100]があったから。その後追いでやってもどうなんだろうっていうのもあったので、僕はやるつもりはあんまりなかったです。
なんとなく読んでて、出版社が「OUTはすぐパロディとかやるからやめましょうよ」って言ったのかなと(笑)。
いや、そういうわけではないんです。パロディについては次にしましょうよ。いっぱい思うところがあるからね、パロディに関しては。
ライターの話が出たところで、OUTって学生のライターから例えばアニパロ作家になったり、花小金井さんみたいにスタッフになったり、ということが多かったと思うんですけど、そこにはどういう背景があったんでしょうか。
投稿しているうちに、その投稿にセンスがあるか、とか、面白いものを書ける能力を持ってるかというのは、大体わかるじゃないですか。で、それがわかった段階で、ちょっと仕事的なことをやってみませんかって声をかけてみて、その人が乗ってくるか乗ってこないかって様子を見る。
どこかで僕らは、一次媒体の、ものづくりの方向性に行きたいっていうのもあったわけです。OUTならではのものをやりたいっていう思い。やっぱりアニメとか漫画というのは、その作品があってこそじゃないですか。でも元の一次媒体は、僕らは作ってないわけですよ。
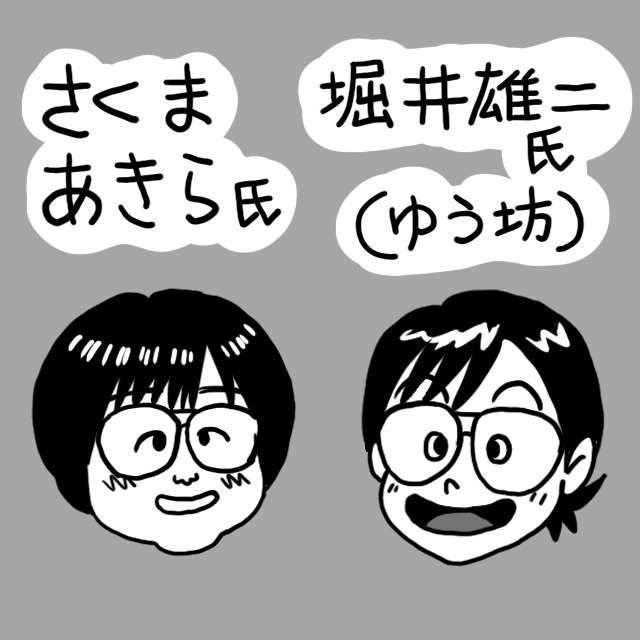
ただ読者投稿に関しては、一次媒体に近いようないろんな企画ができたんです。もちろん最初はさくまさんとか堀井さんとかっていう、すでにライターをやってる人たちがいて、すごい才能があったわけです。だからさくまさんも堀井さんも大ゲームデザイナーさんになっちゃった。たまたまそういう人たちに出会えたということもあるかもしれないけども、それだけじゃなくて、投稿者とか持ち込みをしてきてる人とか、あるいは噂でこの人の作品が面白い、同人誌なんかで面白いよねっていうのを見た時に、これはなかなか才能があるな、センスがあるな、と思ったら「うちでもちょっとやってみない?」って声をかけてみることをすごく心がけてました。
それでうまくいったのが、岩崎摂さん[101]とか浪花愛[102]とか。あと中村(治彦:当時)くん[103]も。中村くんは読者投稿から入ってきてるんだから、うちで仕事するようになった人はそういう経緯の人がすごく多いんですよ。
さっきの南田さんは学生で自分で売り込んできて、それから須田留貧さんと仁最祖義さん[104]たちも学生で、自分で売り込んできた、とOUTに書かれていたんですが…
OUTでパロディ企画とかさ、いろんな企画やってるでしょ。で、仁最祖義と須田留貧が「こういう企画があるんだけど、どうでしょうか」って持ってきたのが、すげえ面白いなって。あの人たちのは群を抜いて面白かったんですよ。何か企画やってくれる?っていうと、すごく面白いいろんな企画を出してくれる。
OUTの編集部がほかの編集部と絶対的に違うところは、企画会議にわけのわからない人がいっぱいいたこと。僕は企画会議を編集部員だけでやるっていう考え方は間違ってると思ってたんです。面白い雑誌とか活きのいい企画というのは、誰が考えるかわからないわけ。だからその窓口は広げておくのがいい。もちろん編集会議もやるよ、編集部員だけの会議もやるけども、企画会議のときには、アイデアを持ってるやつは、読者だろうが関係ない人間だろうがとにかく呼んじゃえと。それでバカ話をしてるうちに面白い企画がでてくるわけで。
だから仁最祖義も須田留貧も企画会議に年中でてたし、それこそアニメ・ジュンさんだって。榎野彦[105]は…作家になっちゃうんですよね、RIIの弟ですよ…彼は当時の仕事の関係で出られなかったけど、話すとメチャメチャ面白い。とにかく面白い意見を出すやつは編集会議に呼べと。で、編集会議のあとに飯を食ったり飲みに行くときも連れてけと。連れてって、酒飲ませて、頭のタガを外して、面白い企画・馬鹿な企画をとにかく言わせる。僕は一人そこで冷めてるわけ。面白いことを言ってもお酒飲んでるとみんな忘れちゃうじゃないですか。だから僕はそれをメモして、こんな面白いアイデアが出てきたよって。で、面白いやつから採用する。
素晴らしい!
だから編集者会議じゃない編集会議。でも逆効果もあるんだよ。だって雑誌の部数がどうだったかとか、どんな企画がウケたかってこともさ、バレちゃうわけですよ。ライターさんとかバイトみたいな人たちにもバレバレになっちゃう。だけど、自分の方から本当のこと・本音を言わないと、向こうは言ってくれないですからね。だからそれは、常識というか他の人から言わせると、かなり異常なシステムだと。
すごいですね。みんなでブレーンストーミングやるだけじゃなくて、ちょっと酒も…
酒も入れる。酒を入れないと面白いのは出てこない。ぶっ飛んだ企画は、ほとんど酒が入ってます。編集会議で次の企画なにやりましょうかって、うんうんうなったって、出てこねえっつうのよ。バカ話から出てくるんだって、そういう企画って。「いや、こんなこと絶対できないだろうな」って思うことから始まるんだよ。そんなことはないんだよ、やろうと思えばできるんだよ。じゃなきゃね、あんな馬鹿な企画やってません。
『Oガンダム』[106]とかさ、あんなの考えられないですよね。勝手に「次のガンダムはこれだ」って嘘の情報流してさ、業界も読者も全部騙そうとしたって。
あれは最高でした。
ちょっとだけしか書いてないですもんね、実はこれは嘘ですって。
発案者はアニメ・ジュンだよ!それは書いてもいいと思います。
最初設定の話があって、しばらく後に小説で、それは霜月さんが書かれていますね。
はい。霜月たかなかはアニメ・ジュンだから。
だからそれを見て、えっ!てすごく思ったんですよ。これは実は次の回の時に言おうと思ってたんです。
そうだよね。次の回の話だよ。
その編集会議の話についてひとつ思ったのが、自分が20代から30代ぐらいになってくると、若い読者である人たちが面白く思う何かから、だんだん離れていくんじゃないかな、と。
離れてきます。それはやっぱ高齢化してきますから。
で、それもあって、その若い人たちをそのアンテナに使っていたのかなって。ですけど、飲みに行った時も馬鹿話を拾う。それは素晴らしいですね。
それをシラフで拾っていくし。
その時だけはシラフで拾うのよ。
丁寧に見ていくと、例えばアニメのカラーページでも「あれ、何かここは急にセンスが変わったな」というのがあって、これはきっと花小金井さんがやったんじゃないかなって。
やっぱり匂いが出るでしょ。それはその通りなんです。
それが僕らがイメージする80年代のデザイン言語みたいな匂いがするんです。それで、例えばRIIさんがやってたページというのは、あんまりそういう匂いがしない。
RIIの話はどこですればいいのかなと思うけどさ、特異な人だったですからね、あの人は。うん、亡くなっちゃったんで言ってもいいか、みたいなところもあるんです。相当僕も喋っちゃったんだけど、これ、『OUT10年史』[107]なんかでいくつか書いてるRIIの事件が、あれ全部本当ですからね。書けないこともあるんだけどさ。
泣きながら、「なんでOUTが出るんだ」と叫んだとか。[108]
なんでOUTが出るんだ?って、なんでOUTが売れるんだ‼ と怒って机をこうやってドンドン叩くんです。これ本当。あとはさ、いいアイデアが出るんだったらいいけど、彼は彼でマゾヒストっていうか、俺はなんでこんなダメなんだとかさ、すごく複雑で屈折してるんだよ。だから、あまりに屈折してるんで腹立ってさ、あるとき僕が酒をぶっかけちゃったりとかさ、いろんなことやってるわけよ。大変な人ですよ、あの人は。
読者ページでのRIIさんはすごくソフィスティケートされていて、とても爽やかなもてなしの良さっていうか…。
そうなんです、だからあの人は偽善者なんです(笑)。読者に対して、雑誌のページの上ではものすごくソフィスティケートされた紳士なんです。でも本人はわりとそれと真逆の人格と言ってもいい。まあ作家によくあるタイプだ。書いてる内容は紳士的なんだけど、本人は人格崩壊者…それに近いものがあるんですよ。しかし、誤解されると困るので、あえて言っときますが、普段はきわめて真っ当な優しい人ですよ。すごい博識だったしね。ただ、酒がはいって酔っぱらったり、なにかの拍子でスイッチがはいると、そうなっちゃう。
さっきの戦争アニメ論争は、実は大徳さんの『OUTLAND』のページに匿名で書かれてきたある読者の投稿を、RIIさんがさらしものにしたっていうところから始まっています[109]。その読者の言うことも色々おかしいんですが、ここまでしなくてよかったんじゃないかって、僕は読んでて思ったんですよね。
そう、この問題は非常に難しい問題だね。やっぱりね、読者をさらし者にしちゃいけないんだよ。編集者っていうのは、そのページをどうするかっていう権力者なんですよ。決定権を持ってるわけだから。絶対に読者よりも権力を持って上に立つ立場になってはいけないんだよ。だからあれに関しては、僕があの記事を見たのは校正の最終段階でどうにも変えようがなかったんだけど、RIIに文句言ったのよ。こういうやり方はよくないよ、つってさ。僕は『READER'S VOICE』で自分が書く批評文は、読者の投稿よりも絶対に分量を減らしていた。多く書くこともできるんですよ。2〜3行の読者の文句に1ページ使っちゃうこともできる。でもそれをやったらおしまいなんだよ。そういう意味で、極端に言えば権力を持ってるんだってことをちゃんと認識してページ作らないと、とんでもない間違いを犯すぞと。でも、そういうことをやらかしちゃうこともあるわけ。
でも、そうした内実を晒すことはなかなか難しいというか、出来ない。本当は雑誌やってる最中に書きたかったんだけど。『暗い根っ子の会』[110]で、かなりからかったけどね(笑)。
そうですね、いろいろ書いてありましたね。読んでてあれも面白かったです。花小金井さんがまた結構いじってる。
そうそうそう。
花小金井は、あいつはすごい能力があったんだけどなあ、結局は違う世界に行っちゃったからさ。大学辞めて、うちの会社に来いよって言って…他からも彼はすごく誘われてるんですよ。でも「教師になります」って言うから、頭にきてさ、花小金井の家に電話したんだよ。
「宮崎県の教育委員会のものです。君の大学時代にアルバイトでやってる仕事が、私たちにわかりました。まずいと思います。君のこの教員資格は認めません」…って。電話の向こうでね、絶句してました。これ、俺の嫌がらせ。
(一同爆笑)
だってまさか先生になるとは思わなかったんだよ。出版業界とかアニメ業界とか、何か関連の業界には行くのかなと思ってたの。めちゃめちゃ詳しいし、頭もいいし、筆力もあるし。どっちかというと、彼は作家になってもよかったんじゃないかなと僕は思ったぐらいだから。なのに学校の先生になるっていうんだ。「へえ…」みたいなさ。つまんねえなーと思っちゃってさ(笑)。「学校の先生になる人なんか他にいっぱいいるじゃん、君みたいな人は違うことやる方がいいよ」って。もちろん、その電話した最後は、冗談だよって話しましたよ(笑)。
だってバイトでライターだったところの編集長からそんな電話がかかってきたら、やっぱりビビりますよ!
ちょっと別の話になりますが『ファンジン紹介ちゃん』というページは、もう本当に黎明期からずっとほとんど休刊まであって、OUTではいちばん長いコーナーになっていました[111]。
はいはい、そうです。
たぶんこのコーナーに影響というか、助けられた人って、特に地方の子がいっぱいいたと思うんですよね。
だからやめなかったんです。だって今みたいにネットとかない時代ですから。同人誌を作ったり、即売会やったりっていう情報なんてほとんど知られないわけですよ。だけども、OUTっていう雑誌はそういう読者たちが買って支持してくれたから続いてきた、というところがあるわけじゃないですか。だから僕はファンジン紹介に関しては絶対に無くすなって言ってた。人気はないんだよ。人気投票やったらいちばん下になるってわかってる。でも、そのOUTの原点というものを忘れちゃいけないよっていう意味なんですよ。
だけど他にアニメ雑誌がいっぱい出てきて、インターネットが出てきてからあんまり意味がなくなっちゃったんだよね。まあネットに関しては、アニメ情報とかパロディとか読者投稿にいろいろな影響を及ぼした部分というのもあって、最終的にOUTが続かなくなった理由の大きな部分ではあるんだけどさ。
例えばこの人(KN)は『ファンジン紹介ちゃん』に出してもらって、作ってた本が売れたって言ってたんです。
載っけたくても分量は決まってるから、たくさん送られてくる中で何を載せるかっていうのは、これはもう編集者の判断なんですよね。
あの当時、ほかにそういうことやってる雑誌ってたくさんあったんですか。
『ファンロード』[112]…ファンロードは後にできたんだけど、『アニメック』ってやってましたっけ。そういうこと。
『アニメック』よりは『アニメディア』でしたね。
確かに『アニメディア』ではやってたか。ただ、あんまりやってない。だって人気ないもん。でもファンに送ってきてもらった中で、これは面白い企画だというのはどこかで耳に入るんです。アンテナに引っかかってくる。だから、無くしちゃいけないっていうのにはそういう意味もあったよね。
その後、そのコーナーの影響…「OUTに載っけてもらって、今こんなことやってます」みたいな人と会ったりしますか?
会ったりはあんまりしてないんだけども、そういう人はいっぱいいるんじゃないですかね。
僕らの興味のひとつがOUTがその後のカルチャーに与えた影響っていうことで、僕らの考えではファンジンのページがすごく大きいんじゃないかって思ってるんですよね。他にも例えばパロディの文化とかもいろいろあると思うんですが、もしああいう地道なところがなかったら、実は地方ではもっといろいろ遅れていたんじゃないかと。
なるほどね。それはとてもありがたい見方ですよ。
同じように本の紹介であるとか、音楽もそうですし、OUTは総合雑誌であるってあちこちで書かれてますけど、そのあたりのあり方については。
僕の理想としては、後から出てきた雑誌で『遊』って、松岡正剛がやってる雑誌[113]。若い時の、まだ全共闘時代の理想は本当はああいう本だったんだけど、サブカル的な部分に関しては『ビックリハウス』も『遊』も、他の雑誌もあんまり取り上げてなかったので。やっぱりそこを取り上げられたらOUTも十分だな、だから他の雑誌が取り上げてないサブカル文化に関して取り上げるっていうことはすごくありましたからね。でもやっぱり今から見ると、カオスなんだよね。「何の雑誌だかよくわかんねえな」みたいなさ。
まさにそれがOUTですね。読者としても、アニメだけの雑誌じゃないことにすごく惹かれたからこそ買っていたというところがありました。
でもね、なんの雑誌なんですかって説明しづらいと困る部分が…、まず、うさんくさい雑誌だと思われる。色々あるんですよ。
これほんとに中学生か高校生の頃に聞かれてたら、「なんか変な雑誌だよ」と答えてたと思います(笑)。もちろん、アニメ文化の中にひとつの確固たる位置を占めていたと思うんですけどね。中学生の頃に、友達から「あんたはアウシタンなのか、ニュータイプ[114]なのか」って訊かれたことがあります。そのぐらいのポジションではあったんだなあと。
それは僕らだって、アニメージュとかニュータイプみたいな、かっこいい雑誌作りたかったですよ!
ええ、そうだったんですか!
それを言っちゃおしまいだけど。
(→ その5につづく)[89] アニメ・ジュン:アニメ評論家。月刊OUTでは『アニメ・ジュンの大発見』『アニメ・ジュンの場外乱闘』また霜月たかなか名義で『鏡の国のアニメーション』などの長期連載を持ち、辛口の評論で名を馳せた。
[90] 米澤嘉博:漫画評論家、コミックマーケット準備会第二代代表。2006年逝去。
[91] 亜庭じゅん:漫画評論家。コミックマーケット創設者の一人。2011年逝去。
[92] '81年7月号『機動戦士ガンダムと騎士道物語』。ガンダムについて西洋騎士道物語の形式と関連づけて論じている。
[93] '80年4月号、ガンダム特集パート2『機動戦士ガンダムの捕虜となった10時間』(白井佳夫)。この号には他にも平岡正明や川又千秋らの評論が掲載されている。
[94] '79年4月号『アニメーションフィーバー"79"』にてアニメ版キャプテン・ハーロックを批判しており、翌号ではそれに対するファンからの反論や同意の投稿が掲載されている。
[95] 南田操:アニメ評論家。OUTでは'81年6月号から'85年5月号まで『南田操のアニメブレイク』、'85年3月号から'88年4月号まで『南田操のアニメDJ』を連載。
[96] '80年12月号から'82年2月号まで、『簡単マンガ時評』と『病気の人のためのマンガ考現学』』を連載。それ以前にも阿島俊名義で吾妻ひでお論を執筆したりしている('78年8月号)。
[97] 『COMIC LIVE DISCUSSION』という企画で、人気漫画家や漫画評論家と対談している。鳥山明(’82年3月号)・高橋留美子(’82年4月号)・細野不二彦(’82年6月号)・米澤嘉博(’83年3月号)・いしかわじゅん(’83年4月号)・魔夜峰央('83年7月号)など。
[98] '78年8月号特集『吾妻ひでおのメロウな世界』
[99] ぱふ:雑草社発行の漫画情報誌。2011年に休刊。
[100] COMIC BOX:ふゅーじょんぷろだくと発行の漫画情報誌。2000年に休刊。
[101] 岩崎摂:漫画家。『MY HOME ギジェ』などのアニパロ漫画を連載する。アウト編集部に「仕事ありませんか」と入っていき、仕事をすることになった。
[102] 浪花愛:漫画家。『シャア猫のこと』や『五右衛門金魚』などのアニパロ漫画を連載する。「浪花愛のカマトトサロン」という副題が柱部分についていた。
[103] 中村治彦:漫画家。『湯島ウラ行進曲』『やにわに同好会』などの4コマ漫画を連載する。後にペンネームを『なかむら治彦』に改名。
[104] 仁最祖義(じんももとよし)と須田留貧(すたるひん):「じんすた」のコンビ名で多くのパロディ企画を担当する。当時の読者の記憶に最も残るのは'85年5月号から始まる『OUTシャイダー』であろう。須田留貧はその後も長くおもちゃ紹介コーナーを連載する。
[105] 榎野彦:ライター。編集部員RIIの実弟。花小金井和典とのコンビで多くのアニパロ小説を発表し、また人生相談コーナー『AOI私を責めないで』も人気を博した。後に鷹見一幸として作家となる。
[106] 機動戦士Oガンダム:'86年3月号。完全独占速報と謳い、巻頭カラー8ページにわたり架空のガンダム作品を特集した。背表紙にまで『機動戦士Oガンダム』と載せているのがすごい。'87年6月号よりパロディ小説を連載。さらに'88年2月号より『機動戦士OガンダムII』も連載した。
[107] 不滅のOUT10年史:'87年5月号、T編集長による月刊OUTの10年史。
[108] これはSIIの記憶違いで、「OUT10年史」によれば、酔っぱらったRIIが「どうしてOUTはこんなに売れるんだ!どうしてオレみたいな人間がOUTの編集をやっていられるんだ!世の中間違っとる!!」と怒ったとのこと。
[109] '82年4月号、OUTLAND『自分の言葉で語るということ(R2)』。'82年2月号のパロディ記事のいくつかが戦争賛美なのではないか、と問う匿名の読者投稿に対し、匿名であることについてR2が痛烈な批判をしている。
[110] 暗い根っ子の会:'82年5月号から連載された、RIIがいかに根暗であるかということを題材にし、読者が自分の暗さを競い合うコーナー。後にRIIファンクラブというコーナーも作られた。
[111] ファンジン紹介ちゃん:'78年3月から'95年4月号まで続いた、ファンジン(同人誌)紹介のページ。
[112] ファンロード:1980年にラポートから発刊された、読者投稿を主体とする雑誌。
[113] 遊:工作舎から刊行された雑誌('71-'82年)。編集長は松岡正剛。「オブジェマガジン」と称し、あらゆるジャンルを融合した独自のスタイルは、日本のアート・思想・メディア・デザインに多大な衝撃を与えた。
[114] 月刊ニュータイプ:角川書店(のちKADOKAWA)から出版されたアニメ雑誌。創刊は'85年3月。

