元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。
公開日:2025年1月26日
今の、鼻を明かすというのとガンダムを馬鹿にしてるという話で、ちょうどいい流れだと思ったんですが、「ガンダムSF論争」ってありましたね。高千穂遥[56]さんが書かれた『ガンダム雑記』[57]という文章に「ガンダムはSFではない」というようなことを書かれたことから始まった一連の議論。でも、OUT誌上の論争では全然ないんですよね。
論争ではないんです。
その高千穂さんの文章を見た読者たちが勝手に興奮していろんな反応をしてしまった[58]。それで高千穂さんが何ヶ月か後にそれを受けて、自分の持っているSF観についてとSF入門者はこういう本を読んだらいいよという、とても真摯で丁寧な記事をOUTに書かれた[59]。この記事を読んで素晴らしいなと思ったんですけれども、この一連の流れをOUT編集部としては一体どう思っていたんでしょうか。
あれに関しては(後で富野監督との)対談をやってね、高千穂さんは「ガンダムはSFじゃないですよ」って言ってます。要するに、SF的に考えた時ネグってる(無視している)部分がいっぱいあるわけ。SFじゃないんですよ。(富野監督も)「科学考証の部分とかSF考証に関してはできる限りのことはやりました。だけど正確な意味でのSFじゃありません」っていうことを言ってる[60]。高千穂さんも、それに対して別に噛みついてるわけでもないわけじゃない。
読者が勝手にやり始めちゃったんですよ。「ガンダムがSFじゃなかったら何がSFなんだ」みたいなことが始まって、高千穂さんまで何か変な標的になって「富野さんをいじめるSF作家」みたいな感じになっちゃったんで(笑)、それはおかしいよねって。それで高千穂さんに書きますかって言ったら、「ぜひ書かせてください」っておっしゃるから、載っけたっていうことにしか過ぎないんですよ。
当時からSFの人たちはめんどくさいっていう、そういう意識が…
それはすごくあったと思いますが、というよりSFというのは、単純に科学的な概念を物語のために設定として使った作品と、最新科学に則って厳密にサイエンスフィクションとして仕立てたSF作品と大きく分けて二つあったわけじゃないですか。ある意味で言えば、高千穂遙さんは、SFというものを、そうした後者のように考えている方じゃないですか。「自分の書くものはSFじゃないけど、本当のSFはこういうものなんだ」っていうSF論者と言っていいでしょう。
そこでさっきのガンダムセンチュリーの話とリンクすると思うんですけど、「ガンダムセンチュリーがこれぐらいできるんだぜ」っていう対象が二つあったのではないかと。ひとつは何も知らない世間。もうひとつは、そのSF的なことをうるさく言ってくる人に対して「いやいや、こういう解釈でこういうことができるんだ」ということがあったんじゃないかなと思ったんです。
もちろん、それはありましたよ、うん。それに、そもそもガンダムセンチュリーは、スタジオぬえと科学ライターの永瀬唯さん[61]の協力があって成立したものですからね。
SFってそんなに偉かったんですかね。
それはね…でもちょっと難しいんだよ、SFの場合は。SFの場合は馬鹿にされても「お前ら馬鹿にするかもしれないけど俺たちはお前らよりもずっと論理的・科学的にやってるんだぜ」っていうのがあったんじゃないですか。だからアニメとは理想がちょっと違うんです。僕はSF好きだったのでSF側の言い分もわかるし。SFを文学として認めないっていう人たちの文学も結構好きだったって部分もあって、難しいよね、そこね。
そうですね。別にこだわらないで、「SFじゃないならそれでいいですよ」って言えば済んじゃう話で、富野さんは結局そう言って終わらせちゃったと思うんですよね。この人(WH)も僕もSFはものすごく好き[62]なので、そのSFマインドの目から見た感じはすごくよくわかるんですけども。
ちょっと、こじれた感じね 。
そうそう。それでもその当時、40年前はそんなにSFは偉かったのかなと思う。逆に言うと、アニメ側のサブカルの人は、SF的サブカルにちょっと憧れを持っていたのじゃないかなというふうにも見えたんです。
「ガンダムだってSFなんだ!」って。
富野さんはね、そんなにSFは軸じゃなかったんですよ。だから、スタジオぬえって超SFの連中[63]をスタッフの中に入れ込んで、科学考証やってほしいって言ったのが、根っこなんだと思う。
SFの人は昔から疎外された人の自意識みたいのがあって、被害者意識が強い。
まあ強いと思いますよ。文学としてまともに扱われてないっていうところがすごくあったから。
OUTはもともとすごく初期にSF特集がいっぱいあってSFから始まっているけど、大徳さんがやられてた頃はあんまりSFってなかったと思うんですよ。
いや、でも僕はもうSFファンどころじゃなくて。さっきも言ったように僕は鉄腕アトムで育ってますから。将来何になりたいですかっていう小学校の時の作文で、僕は「鉄腕アトムのお茶の文博士みたいな科学者になって人類を平和にしたいです」という作文を書いた。
それでずっと科学者になりたくて、だから当然ながらSFに行ったわけです。SFというものが文学として認められてないというSFの人たちの鬱屈もすごくよくわかるし、特に、どっちかというとハードSF[64]の人たちの気持ちがね。
また、決してハードじゃなくても、いい作品ってあるわけじゃないですか。たとえば日本で言うとこの間テレビに出てた筒井康隆[65]とか、星新一[66]とか、文学として自分たちは認められていないって鬱屈はやっぱりあったからね。
筒井康隆もあの頃は大御所というよりは、やっぱりSFの人っていうか。まだ小松左京[67]とかがビッグだった時代です。『日本沈没』が70年代だから。
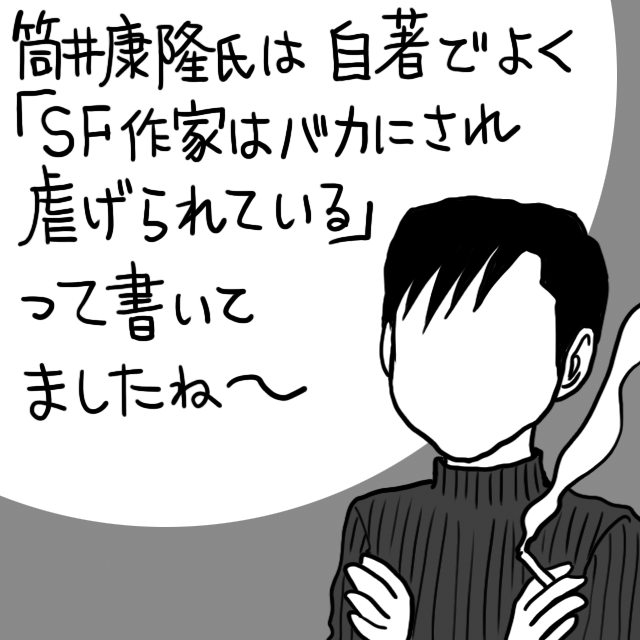
それで筒井康隆が、例えばかんべむさし[68]とかあのあたりと繋がってきてね。なんでOUTにはそのあたりはそんなに載せなかったんでしょう。読者層が全然違ったんでしょうか?
やっぱりね、SFはSFでね、こう一角をなしちゃってるようなところがあるんですよ。そこでOUTみたいな雑誌がそれを組み込むのは相当難しかったっていうのがあります。
今でこそSFっていうのはオタク文化の一部ですけど、当時はもっと別物だった。
だから初期の頃は竹宮恵子さん[69]とか、それこそ ひおあきらさん[70]とか、そういう特集をしてましたけど、そこは許せる接点みたいな感じだったんですかね。
そういうところはあります。でも僕らはSFの人たちに対してシンパシーは感じてた。ただ、正面切ってきちんと論じる・取り上げるというところまで行かなかったっていうことだね。
ガンダムセンチュリーはアプローチは完全にSFで、そういう接点もあるのかな、と。さすがに自分も子供だったから、その辺の空気感…SFとアニメの間の微妙な関係性というのが全然わからなくて。やっぱりSFのやつは偉そうにしてるみたいなのは、いまだにずっとあるので(笑)…。実際偉そうにしているのでよくないんですけど。
SFの人たちは「自分たちは迫害されてる」ってちょっとそういう意識があって仲間で固まる傾向があったんだよ(笑)。だから仲間に入ってる人はいいんだけど、入ってない人がね、横から入っていくのはなかなか難しい。頭がいいからね、基本的にSFの人は。
「お前、ここに入ってこないと仲間に認めてやらないから話もしないぞ」みたいな。
それはあったと思う。あったし、今も…
なくはない。
変に教条主義[71]みたいなところがあるし、エリーティズム[72]もあるし。よくないことです。アニメファンにはあんまりそういうエリーティズムみたいなのは…。
あ、確かにそれはないような気がする。そこはね、SFファンとの大きな違いかもしれないね。
SFの人はびっくりするぐらいエリート意識ありますよね。
エリート意識もあるかもしれないけど、どこまでも科学的、論理的であることにこだわる。だからつまんないこと言うと、すごく突っ込まれるわけよ。お前こんなことも知らないのか、ってなりがちなんです。
硬派なOUT、というテーマで、「戦争アニメ論争」というのがありました。記事を見ていたらふたつきっかけがあって、ひとつはパロディ特集[73]で、東工大のアニメ同好会の企画でおもちゃで戦いをする話と、早稲田大学のアニメ研も愛国主義をパロったような記事があります。それらに対して「そんな企画はやるべきじゃない」という投稿があった。
それからもうひとつが、これはOUTに全然画像が出てなかったので実態がよくわからなかったんですが、『198X』という核戦争を題材にしたアニメーション[74]があって、それは良くないという批判。この二つから始まって、だんだん読者が「自分たちが戦争を娯楽として消費しているのはよろしくないんじゃないか」という自意識で論争して、それが2年ぐらいにわたって『OUTLAND』[75]や『READER'S VOICE』[76]で続いています。この論争についてどう考えていらっしゃったんでしょうか。
これは別にアニメに限らず、小説だろうが映画だろうがあらゆることに関わる問題だと思うんです。例えば日本のアニメはね、僕らはすごく自然に受け止めて育ってきてるかもしれないけど、非常に暴力的である、戦争というものに対して非常に親和的な表現を許している表現じゃないかということを、よく海外、特に欧米から言われたりするわけじゃないですか。で、その問題をどう作り手の人たちが考えているか、あるいは享受するなら、僕らがどう考えたらいいのかっていうことをね、考えなきゃいけないかなというところはあったわけですよ。
ただそれは非常にめんどくさいことだし、どちらかが正しい、絶対だって結論が出るものではないので、非常に複雑で難しい問題だと思います。だけど僕には、この問題をネグっちゃったままでいいのかっていう意識があるから、その愛国パロディの時、あと『198X』の時の投稿として取り上げたんです。なるほどそういう意見もあるんだなと。
暴力描写とか戦争描写というものを僕らが楽しんでエンターテインメントとして見てしまうってことはいかがなものか、ということもあるんですよ。あとはある種のイズムみたいなものにアニメーション・文化的な表現っていうものが利用されてしまうとか。それから、じゃあ戦争のない時代には、フィクションとか文化的メディアは戦争を批判することをできないのか。
極論しちゃえば、暴力描写や戦争描写、そんなものをそのまま楽しんでしまう人間ってのはおかしいんだって言っちゃったら、ほとんどの作品がさ(否定されてしまう)。だって基本的にドラマって葛藤でしょう。その葛藤の最たるものが戦争なのであって、そういうものを題材として間違ってるからって排除しちゃうってどうなの、って部分もあるし。そういう、いい悪いと関係なしに、それをひっくるめた上でもう一度論議してみようっていうのが、僕らの考えたことですね。
でも僕はある程度は暴力表現とか戦争描写というものはあって然るべきと思う。なかったら本当につまらない…それこそ、かつての欧米のいわゆるアニメーションって言われているようなものになっちゃうじゃないですか。
日本のアニメーションがなんでここまで発展したのかというと、やっぱり手塚治虫っていう人が、漫画なんだけども…例えば鉄腕アトムなんかでは第1話からさ、人種差別の問題・ロボットと人間の差別の問題が入ってきたりとか、それまでの欧米のアニメーションには絶対あり得ないような社会的なテーマとか、単純に子供たちが楽しむだけというものではないテーマを入れ込んでいるわけですよ。やっぱり作品というのは、ストーリーがあって、キャラクターがあって、テーマがあって、世界観があるって、この4つで切ってくわけで。
それで、暴力とか戦争というものを取り入れたんだったら、どこかで暴力批判とか戦争批判ってものがないと、ヘタをすると「この戦争は正しかったんだ」とか「この暴力は絶対正しかったんだ」っていうふうに持っていかれちゃう危険性がある。それは間違ってるなって思っている部分が、今でも僕にあるんですよ。
読んでいるとですね、当時、読者の反応に対してちょっとびっくりしている節があるんですよね。こんなに反響があるとは思わなかったって。
それは本当に僕も(そんなに反響があるとは)思わなかった。あのね、読者投稿でいちばんびっくりしたのはね、ガンダムの時に感想文を募集した時[77]に、とんでもない量が送られてきたんですよ。で、あと戦争アニメです。やっぱり皆さん気にしてたんだ、みたいな。
その後、読者からあれに対して言われたりしたことなんてありましたか?
未だに戦争アニメのこととかは、たまに言われることはありますよ。
そのぐらい当時の読者には、やっぱりどこかに響いたのが何十年も経って残っている…。
じゃないんですかね。
他のアニメ雑誌でそういうものを取り上げたところというのは…?
当時はないと思います。ありますかね。なかったような印象ですけど。「なんでそんなことを言うの」っていう方が強いんじゃないですか。
アニメの快楽的な側面じゃないものは、基本的にあんまりアニメ雑誌は取り上げてこなかったのかなという気がします。
すごく批判されたのは、「セーラー服を着た可愛い女の子が機関銃もってバリバリ人を殺すアニメがいいのか」っていう批判があったんです[78]。それに対しては応えるべきだと僕は思うんだよ。こういうことは本当は作り手の人たちの方から言ってほしかったんだけれども、そういう声が上がらないから、じゃあ雑誌としてはちょっと取り上げてみましょうっていう意識はあった。
それは宮崎さんが言われたことだと思うんですけど、それに対して当時そういう…例えば『プロジェクトA子』[79]みたいなものがあって、たぶん作ってる方はすごく反発を覚えたと思うんですよ。「俺たちは面白くてこれやってるし、買ってくれる人もいるんだ」と。そういう正面切って反論したような動きというのは特になかったんですかね。

僕はね、あれに関しては宮崎さんの気持ちも半分わかってて。もちろんセーラー服の可愛い女の子が機関銃もってバリバリ人殺してもいいのかよっていうのは、確かにその通りだと思うんですよ。だけどそこで、いま言われたエンターテインメントの快楽表現を考えた時に、戦争とか暴力というものが目的なのか手段なのか、ということもすごく重要だと僕は思ってます。銃をもった可愛い女の子がバリバリ人を殺すっていうことが目的の作品だったなら、僕はやっぱり否定したいんです。
だけど人間は暴力や戦争というものを快楽・エンターテイメントとして受け入れて楽しんでしまうかもしれないけども、基本はそれはいけないんだよっていう批判的な視点がきちっと入ったうえでの手段なんだとしたらさ、それはそれで、暴力表現や戦争表現や美少女表現といったものをあんまり規制すべきではないって、僕個人の考え方としては思っていた部分があるわけ。
じっさい宮崎駿の作品だって破壊の快楽に満ちてますよね。
だって、『ナウシカ』[80]なんて、このロリコンめ!みたいなところがあるじゃないですか、はっきり言って。
原作のナウシカの戦争するシーンも、宮崎さんが「戦争のシーンってのはこんなもんじゃないんだ。俺に本当の戦争を描かせたらこのぐらいできるんだ」って言って描かれて、すごいシーンだと思うんですけど、やっぱりこの人はそれが好きなんじゃないか、って僕は思っていました。
戦車も大好きだし、軍事オタクだよね、ある意味で。
戦争の快楽をすごく追求してる。そこに自覚的でもあると思うけれど、まあ…
そうだと思うよ。宮崎さんに対しては、そういう意味ではちょっと愛憎半ばしてるところがあるんだけど。つい先日、フィリピンの映画祭で宮崎さんの作品が賞を取ったんですよ。それで宮崎さんがそこの受賞式の会場には行かなかったので、フィリピンの人たちにメッセージで「第二次世界大戦の時に日本人はたくさんのフィリピン人を殺しました。申し訳ありませんでした」って謝ったんですよ。僕は、それは偉いなと思った。
だってこれ、本来ならば政府や国・政治家たちがさ、ちゃんと言わなければいけないことでしょ。第二次世界大戦の時に日本が戦争するに至った理由はいっぱいあるし、日本だけが悪いわけじゃない。だけれども、歴史的事実っていうのがあって、フィリピンを侵略したりいっぱい人を殺したり日本国がそういうことをしたという事実はあるわけで。それをちゃんと日本人が謝罪したのかっていうことに関して、宮崎駿が自分で言ったのは、この人はなかなかすごいなと思いました。
あんまりそういうことをきちんと意識している人は…
いないと思います。そういうところはすごく日本人って甘いんですよ。ドイツなんかと全然違うからね。未だにナチの犯罪とか執拗に追っかけてるしさ、そういうところにこだわってやってるわけじゃないですか。日本は本当にそういうことをやらない。日本でそれを言ったり、やったりすると自虐史観だと言われるけど、それは違うと思うよ。
周りを見てそういう断絶は感じますか。ある世代からあとはそういうことについてどんどんノンポリ[81]になっていったとか。
それはあるね。どんどんノンポリになった。それは僕らの世代の罪が大きいんですよ。結局、連合赤軍とかソ連の共産主義とか世界的な学生運動とかが、あんな結果をもたらしちゃったことに対して、そこに至るまでやっぱり批判的になってなかったんです。あの結果が出て現実ってものを見て「僕らのやってたことが必ずしも正しくなかったんだ、間違った部分がいっぱいあるんだ、ならばどこに問題があったのか?」って、もうちょっと批判的に見る視点をちゃんと持ってなきゃいけなかったのに、僕らが持ててなかったっていう。
それは例えばさ、日本が戦争で敗けた時に、日本の民衆ってそれまで、みんな戦争やれやれって言ってたわけじゃないですか。国民もそうだしジャーナリズムも。なのにあんな結果になっちゃって、ほんとに…反省するって言い方はおかしいけどさ、自分たちがいかに蒙昧で盲目で物事の真実を見ていなかったのかっていうことを初めて思い知った部分がある。それは忘れちゃいけないと思うんだよね。
同じように、学生運動に関してもそうなんですよ。あの頃ああいうふうにやったことに対してきちんと批判的に見る視点もちゃんと持ってなきゃいけないなって思っていて。単純に今の日本の右傾化がどうのこうのっていうものじゃないね。もっと根深い部分なんだよね。
また論争の話で。いくつか面白い論争があるんですけど、僕が面白いなと思ったのは、85年8月号、『Zガンダム』の頃ですね。富野監督が自分で「Zガンダムは失敗作だ」みたいなことを言っちゃって、ファンから「そんなことを言ったらダメだろう」という投稿があった[82]。それに対して大徳さんが「誰でも10割バッターじゃないんだし今まですごいことをしてきたんだから、そこは苦しい時に助けてあげるのが本当のファンでしょ」って言われた。で、その直後に富野さんのインタビュー[83]があって、富野さんから「あなた(大徳編集長)がそんなことを言っちゃいけないんだ、批判させろ」と。「そんな甘えた視点なんかいらないし、そんな人はインタビュアーとして認めない」みたいな言葉があって、僕はこの一連の流れを見た時に本当にシビれたんですよ。僕が今あらすじを言っちゃいましたけど、当時どういうふうに考えられていたかということをお聞きしたいんです。
正直に言うと、Zガンダムに関しては僕も失敗だと思ってるんです。失敗なんだけども、富野さんがそれを失敗だって言っちゃうっていうのもなんだかなと思った部分が、やっぱりあるわけ。それで、Zガンダム批判が…なんでファーストガンダムと違うんだよとかさ、それを含めていろいろな批判がバーッて出てきて、あまりにもみんな付和雷同的に行っちゃったんで、それはちょっとおかしいんじゃないのかっていうのが僕の真意なんですね。だから僕の中には別にそんなに富野さんを擁護するって意識はないんです。
富野さんがおっしゃってるのは全くその通りだと僕も思いますよ。「こんな中途半端なところで俺を弁護してくれるな」なんてその通りだと思うし。だって実際にZガンダムはさ、カミーユが最後に頭がおかしくなっちゃうラストを映画の時に変えてるじゃないですか。要するに富野さんにも迷いがものすごくあるんです。
でも僕は逆にそういう迷いがあるからこそすごくいいなって思っている部分もあるわけです。作品として完成されてないというか、やっぱり人間が作ってるんだな、人間が書いてるんだなっていう、むしろそういう好印象の方が強いんですよ。だから付和雷同するなと。もう一度自分の頭の中でよく考えてから物を言えよ、というのが僕の本音です。
それを読者に対して言いたかった。
読者に対して。それは自分に対してもそうだしね。自分がこの作品、Zガンダムが傑作かどうかという結論付けって、できてなかったし。それは間違いなくファーストガンダムはすごい傑作だなっていうのはあったよね。でも、じゃあ無謬なのか、疑問点がないのかと言ったら、そんなことはないわけで。
それは例えばナウシカの時もそうなんです。ナウシカはみんな素晴らしい素晴らしいって言って、確かに素晴らしい。だけども、おかしな部分はあるよっていうのが僕にはあった。特にラストの部分なんか、僕はあんまり納得しなかったんですよ。何か宗教的になっちゃってる。民衆が一緒に戦おうよって言ってるのに、ナウシカが勝手に一人で突っ込んでいく特攻みたいな話になっちゃってて、それはいかがなものかなって。やっぱりあそこで民衆と共闘すべきだよなって僕は思ったんです。原作の漫画の方のナウシカはもっと複雑な話でそんなに単純な話にはなってないんだけど。
宮崎駿の考え方がある意味では実写映画における黒澤明みたいになってしまう。天皇みたいになって、みんな無批判に宮崎駿作品だから絶対正しいんだ、優れてるんだっていう風になってしまう。その流れというのは僕はあんまり承服しない。
宮崎さん自身もそう思ってないですよね。「俺の言うことをみんな聞いてくれたらハッピー」では絶対ないですよね。
そうそう。
富野さんとのそのインタビューで面白かったのは、富野さんの懐ですね。すごく深みがある、覚悟のある人だな、と思ったんです。
いや、もうそれはすごい。大変な人です、あの人は。うん、すごい人だと思いますよ。
そういう人と話をする時には構えていくんですか。
でもそれは富野さんがすごい人だっていうのは半分わかっててやってましたからね。僕はあんまり構えて行かなかったですけどね。

富野さんの話でいちばん面白かったのは…これは次の回になるかもしれないけど、セイラさんのヌード[84]ね。あれに関しては本当に今から思うといろいろあってね、失礼な話だったなと思うわけよ。だって女性のヌードっていうのはね、例えば「あなたヌードになってください」って説得して、本人が納得する、で、事務所も納得する、というので載せるんですよ。
あのセイラさんのヌードに関しては、当然サンライズにも了解を得てないし、富野さんにも安彦さんにも了解を得てないんですよ。勝手にやったんです。編集部でそんなヌード載せるべきじゃない、いや載せたいっていうので大論争になって、僕は載せる方の側で。こんなことを言っちゃうとあれですけど、あんなに大反響を得るとは思わなかったけど、正直やっぱり売れると思ってたんですよ。
ヌードに関しては森雪のヌードをヤマトでやったことがあるから、別にいいじゃんって思ってたのね。それぐらいラジカルなことやらないと、あの当時すでにちょっとOUTはラジカルじゃないという批判も出てきたり、売り上げの部数がきつかったというのもあったしで、あえてやっちゃったっていうところもあるんですよ。
でも当然サンライズや富野さんたちから怒られると思ってたの。そしたら何も言われなかったんですよ。ただ富野さんに会った時に「すみません、セイラさんのヌードやっちゃって」って言ったら、
「いや、俺は怒ってる」
って言うわけよ。だけどなんで怒ってるかっていうと
「なんでセイラはもっと綺麗に描かなかったんだ」
って。それはびっくりしましたよ。この人の懐ってなんなんだろう、ってさ。OUTの周年企画のメッセージでも、その事を富野さんが書いていたでしょ[85]。
取材してていちばん哲学的な深さを感じた人はね、高畑さんです。富野さんもそうなんだけど、あの人は言ってることはすごいことを言ってるんだけど、話があっち行ったりこっち行ったりして、何を言ってるのか分からなくなっちゃう時があるでしょ。高畑さんはそういうことはほとんどないんですよ。
びっくりしたね。こういうアニメーションの演出家がいる。まだそれほど高畑さんが有名じゃないころですよ。 僕は『母を訪ねて三千里』ってアニメすげえなと思ってたんで。あと『未来少年コナン』とかさ。やっぱりあのへんの高畑さんものすごいんですよ。めちゃめちゃ考えて作品をつくっている。すごいインテリだったしね、高畑さん。
『セロ弾きのゴーシュ』[86]という作品をOUTですごく丁寧に取り上げてるところがありました。
あれはだから、僕が高畑さん気に入っちゃったから。『セロ弾きのゴーシュ』がつくられて、観たわけ。で、あんまりヒットしないだろうなと思ったんだけど(笑)、「特集やっちゃいましょうよ」って特集をやった[87]。そういうね、横暴なこともやってるんです。
大徳さんの署名記事でけっこう長い文章を書かれていたんですよね[88]。それを見て、この作品観たいなと思ったんですけど、ちょっと今そのアニメ観られるのかはわからない。
観られます。今でも上映よくやってるし、DVDも出てるし。宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』もいいけど、それ以上にアニメの方がいい珍しい作品ですよね。
(→ その4につづく)[56] 高千穂遙:小説家。スタジオぬえの設立者の一人。代表作に『クラッシャージョウ』シリーズ、『ダーティペア』シリーズなど。
[57] '80年4月号『ガンダム雑記』にて、三話までは「SFの傑作となりうる要素を秘めた作品」とし、「五話を過ぎたあたりから…今ひとつ、SFになりきれない」「ガンダムも偉大な失敗作だったようだ」と評している。ただし読者に対して「局に嘆願書をだされるのもいい。ファンクラブをつくられるのもいい。しかし、それよりもなお、スポンサーの商品を買ってもらいたい。それだけが唯一、作品をまっとうに完結させる手段なのだ」と書いており、単に作品を切り捨てている内容ではない。
[58] 高千穂氏のもとに反論の手紙が多く届いたようだ。
[59] '81年2月号『SFを考えるー巨大ロボットアニメを軸としてー』。7ページにわたる高千穂の文章と、彼の推薦する海外SFのリストが掲載されている。
[60] '81年4月号『高千穂遙 vs 富野喜幸 デス・マッチ対談』富野自ら「SFというのは、ちょっと違うよ」と述べている。
[61] 永瀬唯:評論家・科学技術ライター・SF史家。
[62] 念のため、OUT勝手連のWHとSIIは、かなり重度のSF好きである。
[63] スタジオぬえ:'70年代に設立された、SF作品を中心とした企画制作スタジオ。メンバーは数多くのSFアート作品やアニメーション作品のメカ設定などで活躍した。
[64] ハードSF:SFのサブジャンル。なんらかの(架空を含む)科学技術を中心にストーリーを構築し、科学的知識の正確さを重視する。
[65] 筒井康隆:ナンセンスで毒のある奇想小説・実験小説から幻想文学まで、多くの傑作がある。短編「残像に口紅を」が近年SNSで再発見されヒットした。
[66] 星新一:ショートショート(短めの短編小説)の名手として知られる。『ボッコちゃん』など。
[67] 小松左京:科学知識に裏打ちされたスケールの大きな作品で高く評価された。代表作は『日本沈没』『復活の日』。
[68] かんべむさし:日本SF草分け時代の人気作家のひとり。『38万人の仰天』『ポトラッチ戦記』など。
[69] 竹宮恵子特集:'79年1月号。
[70] ひおあきら特集:'78年5月号。
[71] 教条主義:なんらかの教えに従うことをきびしく強いる価値観のことだが、ここでは、「SFファンを名乗るなら1000冊読め」というようなファンダムの掟めいたものが念頭にある(さすがに近年はそういう人は減ってますが)。
[72] エリーティズム:優れた人間に社会を運営する権利があるという考えだが、ここでは単に「優越感」くらいの意味で使われている(雑ですいません)。
[73] パロディ特集:'82年2月号『初笑いアニメ・パロディ大特集』。『近未来戦争19Z5』はリカちゃん人形とガンダムのモビルスーツのプラモデルを使って、B国に侵攻された北海道を解放するというストーリー。また『アニコムZ・自衛戦隊ジャパニーズ』(早大アニメ同好会)は架空のテレビシリーズの特集という体のパロディ記事。
[74] FUTURE WAR 198X年:'82年公開の劇場アニメーション。米ソの冷戦激化と核戦争を題材にして制作された。制作途中に「戦争アニメを作らせないようにしよう」という反対運動が展開された。アウトでは'82年4月号のアニメ・ジュンと南田操の対談の中で一部この問題にふれられている。https://ja.wikipedia.org/wiki/FUTURE_WAR_198X年#
[75] OUTLAND:’81年11月号より'83年4月号まで連載された、OUT編集長Tが自分の思うところを記すコーナー。「編集者と読者のみなさんを結ぶ、がらにもなくマジなページ」と記されていた。
[76] OUTREADER'S VOICE:'82年11月より始まった投稿コーナー。他のコーナーと異なり、アニメ作品の批評や社会批判・読者の悩みなど、シリアスで真面目な投稿が主体であった。コーナー名を変えながらも休刊時まで続いた。
[77] '81年2月号。「応募総数697通、原稿用紙にして6000枚。さすがガンダム」と書かれている。
[78] '86年8月号『ラピュタそして現在のアニメのこと 宮崎駿からのメッセージトーク』。アニメ誌合同の会見を伝える記事で、宮崎は「作り手にしたって、セーラー服が機関銃撃って走り回ってるようなの作ってたら、絶対だめだと思うんです(笑)」と述べている。元の発言趣旨は狭い層をねらった安易な企画を批判するものだが、安易という部分の裏にはエンターテイメントの快楽表現に対する自覚的批判もあるといえよう。なお戦争アニメ論争はこの宮崎発言より前であり、宮崎発言がきっかけになったわけではない。
[79] プロジェクトA子:創映新社製作のアニメ映画。’86年6月21日に松竹富士系にて公開。タイトルはもちろん、ジャッキー・チェン主演映画『プロジェクトA』のパロディ。 https://ja.wikipedia.org/wiki/プロジェクトA子
[80] 風の谷のナウシカ:宮崎駿原作・監督の劇場アニメーション。'84年3月公開。
[81] ノンポリ:政治的な信条・主張をとくに持たないという意味でいまも使われる言葉だが、学生闘争の時代には「ノンポリ」であることは悪とされ、きびしく断罪された。
[82] '85年8月号 『OUTREADER'S VOICE』の読者投稿「富野さんへ言いたい事」
[83] '85年9月号『機動戦士Zガンダム 総力大特集 富野由悠季監督に聞く』
[84] セイラさんのヌード:'80年3月号に掲載された『悩ましのアルティシア』というヌードイラストのポスター。すさまじい反響で同号は増刷をした。また衝撃を受けた読者から『悩ましのシャア』『悩ましのキシリア』などのヌードイラストの投稿が続々と送られてきた。
[85] '87年5月号(創刊10周年記念号)、祝賀メッセージ集。「怒りの富野ソー監督」という名のもとに、「オジサンは裸は好きですよ。だけどね、ていどってもんがあってね、オジサンは気持ちEーィ裸じゃなけりゃ、ボッ、キーしないんだよね。」という、懐の深い祝賀メッセージが掲載されている。
[86] セロ弾きのゴーシュ:作画専門のオープロダクションが自主企画・制作したアニメーション映画。原作:宮澤賢治、監督:高畑勲。
[87] '82年7月号。
[88] '81年1月号『さりげなき大傑作 "セロ弾きのゴーシュ"を讃えて』(大徳哲雄)
[61] 念のため、OUT勝手連のWHとSIIは、かなり重度のSF好きである。
[62] スタジオぬえ:'70年代に設立された、SF作品を中心とした企画制作スタジオ。メンバーは数多くのSFアート作品やアニメーション作品のメカ設定などで活躍した。
[63] ハードSF:SFのサブジャンル。なんらかの(架空を含む)科学技術を中心にストーリーを構築し、科学的知識の正確さを重視する。
[64] 筒井康隆:ナンセンスで毒のある奇想小説・実験小説から幻想文学まで、多くの傑作がある。短編「残像に口紅を」が近年SNSで再発見されヒットした。
[65] 星新一:ショートショート(短めの短編小説)の名手として知られる。『ボッコちゃん』など。
[66] 小松左京:科学知識に裏打ちされたスケールの大きな作品で高く評価された。代表作は『日本沈没』『復活の日』
[67] かんべむさし:日本SF草分け時代の人気作家のひとり。『38万人の仰天』『ポトラッチ戦記』など。
[68] 竹宮恵子特集:'79年1月号。
[69] ひおあきら特集:'78年5月号。
[70] 教条主義:なんらかの教えに従うことをきびしく強いる価値観のことだが、ここでは、「SFファンを名乗るなら1000冊読め」というようなファンダムの掟めいたものが念頭にある(さすがに近年はそういう人は減ってますが)。
[71] エリーティズム:優れた人間に社会を運営する権利があるという考えだが、ここでは単に「優越感」くらいの意味で使われている(雑ですいません)。
[72] パロディ特集:'82年2月号『初笑いアニメ・パロディ大特集』。『近未来戦争19Z5』はリカちゃん人形とガンダムのモビルスーツのプラモデルを使って、B国に侵攻された北海道を解放するというストーリー。また『アニコムZ・自衛戦隊ジャパニーズ』(早大アニメ同好会)は架空のテレビシリーズの特集という体のパロディ記事。
[73] FUTURE WAR 198X年:'82年公開の劇場アニメーション。米ソの冷戦激化と核戦争を題材にして制作された。制作途中に「戦争アニメを作らせないようにしよう」という反対運動が展開された。OUTでは'82年4月号のアニメ・ジュンと南田操の対談の中で一部この問題にふれられている。https://ja.wikipedia.org/wiki/FUTURE_WAR_198X年#
[74] OUTLAND:’81年11月号より'83年4月号まで連載された、OUT編集長Tが自分の思うところを記すコーナー。「編集者と読者のみなさんを結ぶ、がらにもなくマジなページ」と記されていた。
[75] OUT READER'S VOICE:'82年11月より始まった投稿コーナー。他のコーナーと異なり、アニメ作品の批評や社会批判・読者の悩みなど、シリアスで真面目な投稿が主体であった。コーナー名を変えながらも休刊時まで続いた。
[76] '81年2月号。「応募総数697通、原稿用紙にして6000枚。さすがガンダム」と書かれている。
[77] '86年8月号『ラピュタそして現在のアニメのこと 宮崎駿からのメッセージトーク』。アニメ誌合同の会見を伝える記事で、宮崎は「作り手にしたって、セーラー服が機関銃撃って走り回ってるようなの作ってたら、絶対だめだと思うんです(笑)」と述べている。元の発言趣旨は狭い層をねらった安易な企画を批判するものだが、安易という部分の裏にはエンターテイメントの快楽表現に対する自覚的批判もあるといえよう。なお戦争アニメ論争はこの宮崎発言より前であり、宮崎発言がきっかけになったわけではない。
[78] プロジェクトA子:創映新社製作のアニメ映画。’86年6月21日に松竹富士系にて公開。タイトルはもちろん、ジャッキー・チェン主演映画『プロジェクトA』のパロディ。 https://ja.wikipedia.org/wiki/プロジェクトA子
[79] 風の谷のナウシカ:宮崎駿原作・監督の劇場アニメーション。'84年3月公開。
[80] ノンポリ:政治的な信条・主張をとくに持たないという意味でいまも使われる言葉だが、学生闘争の時代には「ノンポリ」であることは悪とされ、きびしく断罪された。
[81] '85年8月号 『OUT READER'S VOICE』の読者投稿「富野さんへ言いたい事」。
[82] '85年9月号『機動戦士Zガンダム 総力大特集 富野由悠季監督に聞く』。
[83] セイラさんのヌード:'80年3月号に掲載された『悩ましのアルティシア』というヌードイラストのポスター。すさまじい反響で同号は増刷をした。また衝撃を受けた読者から『悩ましのシャア』『悩ましのキシリア』などのヌードイラストの投稿が続々と送られてきた。
[84] '87年5月号(創刊10周年記念号)、祝賀メッセージ集。「怒りの富野ソー監督」名義で、「オジサンは裸は好きですよ。だけどね、ていどってもんがあってね、オジサンは気持ちEーィ裸じゃなけりゃ、ボッ、キーしないんだよね。」という、懐の深い祝賀メッセージが掲載されている。
[85] セロ弾きのゴーシュ:作画専門のオープロダクションが自主企画・制作したアニメーション映画。原作:宮澤賢治、監督:高畑勲。
[86] '82年7月号。
[87] '81年1月号『さりげなき大傑作 "セロ弾きのゴーシュ"を讃えて』(大徳哲雄)

