元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。
公開日:2025年8月x日
Nさんも漫画は好きだから、和田慎二さん[53]の作品の記事の時とか…のちにいろんな漫画家さんが載るscrap voiceのゲストのページ[54]の依頼、あれも実は自分だけじゃなくて、Nさんが一生けんめい探してやってくれたのもあるし。吾妻ひでおさん[55]もよく引っ張ってきたよね。あれはNさんです。『超人ロック』[56]もそうだよ。
超人ロックは、連載していた『少年キング』がなくなっちゃって、どうしようってなった時に、聖さんの当時のマネージャーさんがいろんな出版社に声をかける中にみのり書房もあって。Nさんが、「うちはこういう雑誌だから1回で8ページくらいしか取れないんですけどいいですか」っていったら、「いいですよ」って言ってくれて決まった。
その後に、Nさんがいきなり私に
「小林くん、ロック好きだよね」
「好きですけど、なんですか」
「今度やることになってさ。担当して」
って、決めてから言ってきた。
で、「担当して」って言われて…。さっき出た、芦田さんに初めて会って緊張してるのと同じで、それは、聖さんのことは緊張するよ。当然こっちも、『超人ロック』がもともとOUTで取り上げて有名になったのは知ってるし。だから向こうも「OUTで」って言ってくれたわけで、それはわかってるから。もうめちゃくちゃに緊張しましたよ。
その後もいろいろあって、『超人ロック」の生誕50周年の時にやった米沢嘉博記念図書館のイベントにも関わらせてもらったりとか。聖さんのお別れの会の時に冊子を作ったんだけど、少年画報社さんに頼まれて私が作らせてもらったんだよね。それもみのり書房で担当させてもらったからっていうのもあるし。自分の人生の中では大きいよね。
結局、ちゃんとした漫画連載の担当をやったのは、聖さんだけだからね。でね、後でファンイベント(※2011年に開催した「超人ロック SPECIAL NIGHT 2011」)をやらせてもらった時に、聖さんから言われたんだよ。
「これまでずっと長くやって、担当はいっぱいいたけど、たぶん小林くんぐらいだよ、あれやってくれ、これやってくれって言ったのは」
言ったんですか?
うん、言ってた。あの当時は怖いもの知らずで、漫画の担当が何かなんてまるで知らないわけ。やったことないんだから。でも『超人ロック』は好きで読んでたから。
「これまで読んできたロックじゃないロックが見たい。私の見たいロックはこうなんですよ!」
って言って、全部じゃないけどそこからいくつか要素を抜きだして、『聖者の涙』になった。それは今でも嬉しいし、後に聖さんがそういうことを言ってくれたのはありがたいな。たぶん『超人ロック』の歴史の中でも変な編集者の1人だよね。
ふつう漫画の担当をやったことないんだったら、それはもう作家にお任せですよね。
そうそう。でもさ、自分が読みたい『超人ロック』があるわけ。自分もSFが好きだったから、それまで読んできたSFの中で「あれが好きだ」っていうのをぼそっと言うわけ。すると聖さんはSFが大好きでもっと前から読んでる人だから、わかったんだろうね。その中で自分がやってみたかった、チャレンジできそうなことを取り上げて作ってくれたと思うんです。
でもね、後でSNSとかで書かれたんだけど、アシスタントさんに文句をいわれたの。「ロック」の中で一番めんどくさい背景を頼んだのが小林さんだって(笑)。1話か2話かな、見開きで後ろに廃墟があるやつ。私が勝手なイメージとして「こんな風景が」って言ったことを、聖さんがご自分の中で膨らませてラフを描いてアシスタントさんに渡したのかな。それがめんどうだった、と。そういうのを描いていただいた。いまだにありがたいなと思います。
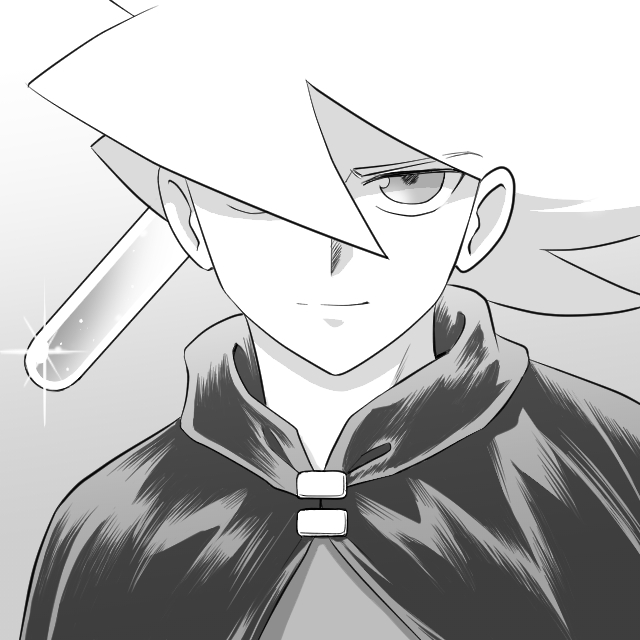
タイミング的には『超人ロック』もちょうど編集部が2人になった時で、担当するページをいかに減らすかっていう意味もあるわけ。他にも小説のページが増えてるでしょ。良い悪いじゃなくて、編集担当としての仕事はあるけど、自分で全部書かなくていいからありがたいんだよね。
でも投稿のページはそんなに減らしてないですね。
減らしてない。だからNさんも私も、投稿ページをやめたらダメだってわかってたんだろうな。この前の大徳さんのインタビューの中でも言ってたけど、投稿ページはなくしちゃダメだって。自分たちの持ち球・決め球として誇れるもの、アニメージュとかニュータイプ[57]・アニメディア[58]にはないものって他にないんだよ。いくら変化球でアニメの記事を作っても、しょせん読む側としては紹介ページであってそれ以上ではないから、番組の本編を見たらおしまいだもん。そこから繋いで来月も読んでもらいましょうっていうのは難しい。
そういう意味では投稿ページってすごいよ。投稿者がいなかったらダメなので、本当に読者が投稿してくれたことに感謝しかないんだけど、でも、よくみんなハガキ書いて送ってくるよね。
本当ですよね。
いや、君たちですよ。
よくやったなって思います。でも、僕らもそれなりに頑張った人たちですけど、例えば首藤真司さん[59]とか長い年月、ずっと載ってる人がいる。
首藤くんもそうだし、当然そういう子たちってネタがいっぱい溢れるんだろうね。イラストにしても文字ネタにしても5枚・10枚書いてきて、それがまた面白かったりして、1コーナーに2枚とか載っちゃうわけだけどさ。選んでる側としては、本当は常連は作りたくないんだよ。みんなが等しくっていうのがいちばん理想で、でもやっぱり面白いかどうか、こっちにはまるものがあるかってなると…俗に常連投稿者って人たちは、われわれ編集側を見てるのかな。狙ってるとこがあるよな。
それは狙ってますね。この人だったらこういうのが好きだ、このネタはこの人じゃないな、みたいな。
やっぱりあるんだ。
ありますね。
我々はそっちを知りたいよ。いつだったか、大阪かな、アウシタン[60]の飲み会に呼んでいただいて…今でいうオフ会ですよ。そこで飲んでたら、当時のある常連投稿者にボソっと横で言われたんだ。「今月号のあのアニメの紹介ページって、小林さんですよね」って。アニメの紹介ページには担当者の名前は書かないんだよ。なのに当てられたの。
「えっ」と思ったら、また違うページの話をされて「この時は調子悪かったんですか」って言われた。「え、なんでわかるんだよ、あなたは!」って。…本当にびっくりしたよね。えっ、読者ってそこまで読んでるのって。
その時にあらためて思ったのが、「編集者って、見透かされてるんだ」と。手を抜いてる暇はないんだ…もちろん手は抜いてないんだけど、最後まで全力を出さなきゃいけないんだ、と。どこかで自分の体調が出ちゃうってのは当時は気づいてなかったの。もちろん体調の良い悪いはありますよ。でも、記事に出てるなんて思ってないから。あれは衝撃…びっくりしたし、ありがたかったなと思う。それを言われなかったら、どこかで鼻を伸ばしすぎて、やがてポキって折られてると思う。
たぶんOUTだけじゃないとは思うけど、読者がそこまでちゃんと見て感じてくれてるんだなと思ったのは、今でもいろんな仕事させてもらってるけど、そのベースになっているのは間違いないですよ。
自分がこの年齢になって読むと、編集部の人が減って大変だったんだけど、でもそんな時に弾けたんじゃないか、あるいは、仕事をだんだん覚えてきて自由にやっていいんだ、みたいな感じに小林さん自身がなっていたように見えるんです。
アニメ記事に関してはそういう慣れはありますよね。自分が担当ページを持ってなくて、「このページやって」と頼まれる時って、使える素材は決まってて、メーカーさん・制作会社から来る場面写真はこれだよ、これで組んで紹介してねっていうことなんだけど、自分が好きな作品をやらせてもらえるようになってくると、向き合い方が変わってくる。
あの頃は、自分でこの話数の…予算があれば1話まるまる焼けるけど、ほどんど半パート…Aパート・Bパートのどちらか決めて、編集長に許可をもらってOUTの予算でフィルムを焼くわけ。それをぐるぐるフィルムを回しながら、好きなカットを切りとって、それを雑誌に載せる。でもそれは、好きなコマを載せられるっていう嬉しさと同時に、フィルムを焼くのに予算が使われているってことを背負わなきゃいけない。いかに元を取るかってことも含めて、ここが面白いんだっていう自分の気持ちをどう読者にぶつけるか。
例えば『ラムネ&40』[61]って、九州だったかな…そこでは放送してなかったんだよね。ところがそこに住んでいる読者から「面白そうで見たくてたまらなかったんです。それでVHSが出たときに買っちゃいました」って投稿が来たときに、嬉しかったもん。自分が面白いと思ったのが伝わったんだって。そういうのが重なって、徐々に自分の「好き」をもっとこういう風に見せようってのが出てきたのかなと思う。
アニメではないんですが、'92年の12月号にF1特集[62]というのがあります。
ああ、これは完璧に私の趣味ですね。
これはすごくOUTっぽいなと思ったんです。サブカルっていう感じではないですけど、さっき言った女子中学生がターゲットでそこのコアは変わらないのに、突然この特集が入ってくる。しかもこの福井利行さんって方のインタビューがすごく面白い。F1の音を録音して、それをCDにしている、その録音の方の話。
おー、そうそう。当時'92年、まさにセナとかマンセルの時代[63]だけど、日本中でF1ブームがあって、F1の音を聴かせるっていうのはその中の企画なんだよね。で、福井さんはその音をぜんぶ録ってた方なんだけど、この方が井上喜久子さんのアルバムのエンジニアだったの。私が喜っ子さんのレコーディングにお邪魔させてもらっている時、スタッフさんと雑談をしてるなかで、「いつもいるエンジニアさん。実はこの人ね、F1の音を録ってるんですよ。海外でも」って。「えっ、どこで録ってるんですか」って話を聞いて、じゃあ取材させてくださいって、この記事になるんです。
結果的にこの記事がいま読むとめちゃくちゃおもしろい。このコースではどこにマイクを置いたらいい音を録れるんだ、とか。
そうそう、そんなマニアックなことに興味がある人、なかなかいないよね(笑)。F1の専門誌でもやってないんじゃないかな。今でもこれはいい、面白い記事だと思います。
この後のページにはF1エッセイ漫画も載っています。
藤臣柊子さん[64]ね。「実は私もF1好きなんですよ」っておっしゃってくださって、描いてもらった。それからたけばしんごさん[65]は今はアニメの設定の仕事されてますよ。たけばさんも、伊東岳彦さん[59]のスタジオに原稿を取りに行っていた時かな、F1の話で盛り上がって、「じゃあ描いて」って描いてもらった。あとはこの時期、「絵ぇじゃないか」とかで、F1のネタがいっぱい来てたんだよ。それもあって、いけるんじゃないかと思った。
それはたぶん、この頃エッセイがいっぱい載っているページ(scrap voice[66])があって、その中で最初の頃はMさんもF1のエッセイをいろいろ書かれていたのもあるんじゃないでしょうか。
そう、私も書いてた。だって私、無理やり鈴鹿に取材に行ってるからね。月刊OUTでF1の取材に行ってるんだよ。[67]
私も男だから、マシンとかスピードとか男連中が好きなのはわかってたけど、でも女性は女性で、また違う方向性があるかなと思ってたの。そしたら、女性の投稿者はF1パイロット(ドライバー)、そういう側面で楽しんでいて、セナのファンとかそういう人たちがいっぱいいるっていうのがわかってきて、だから入り口が違うんだよ。オタクってさ、好奇心を刺激するものなら、なんでもいいんだよね。それでNさんに話したら「いいよ」って。やっぱりOUTがいろんなものに手を出し始めたころだよね。まあ、もともとOUTは、サブカル誌だから。
流星王子TOMMY : 元は芦田豊雄による'88年2月号表紙のオリジナルキャラクター。'92年5月号で「オリジナルアニメ企画発動」という冗談記事が掲載されると、おもしろがった読者が架空の放映内容への感想などを投稿し、連載コーナーとなる。事情がわからない新規参入の読者から本気の問い合わせが来ることもあった。記事の連載中にCD化の企画書を作り、ついに豪華キャストによるドラマCD制作・発売へと至る。
OUTはこの後もゲームの記事をやったり、いろんなことをやる。それが『流星皇子TOMMY』につながると思うんですが、これも冗談企画みたいなものに芦田さんが乗ってくれて、CDを作りましょうって言って、企画書を制作会社に持ち込んだと。
よくやったよね、あれ。本当に企画書を作って持ち込んだんだよ。
OVAのビデオのページがあるけど、当時よく宣伝で来てくれていたSPE・ビジュアルワークス(後のアニプレックス)の担当さんと色んな話をしてて、冗談半分で「芦田さんとこんなことを誌面でやろうと思ってるんですよ」って言ったの。そしたらノってくれて、「CDぐらいだったらなんとかなるんじゃないですか」って社内で検討してくれた。それで芦田さんが喜んじゃって。で、HEGEとかその当時の自分と同じ世代ぐらいのライターさんたちとみんなでああだこうだって揉んで、冗談も言い合って…もう好き勝手を言うわけですよ。
音響監督は誰になるんですか。って聞いたら、千葉繁さん[68]!それで、「キャスティグのイメージを下さい」って言われたんで、ああだこうだと勝手に書いて出したら、「いいんじゃない」って通っちゃって。それで現場に行ったら本当に皆さんいらっしゃってて、やってくださって、びっくりだよね。
イベントの記事もありましたね。[69]
僕はレコーディングに行きましたよ。
そう、百万頭の動物って、みんなで歌ってね。
「あー」とか歌ったりして。それで最初のうちはソニーの方が指示をしてるんですけど、だんだん最後の方になったら小林さんがずっと仕切ってる。
え、私だっけ?全然覚えてない。
今回はこういうやり方で声を出して、みたいなところまで小林さんがやってました。
好き勝手やってるよね(笑)。本当にありがたいのが、これをやったおかげか、OUTが休刊したあと、別の取材で千葉さんに合うじゃない。その時に私のことを覚えてくださっていたの。いまだに私は自慢ですよ、このTOMMYは。
記事に載ってるかな。椎名へきるさん[70]が出てくれてて、彼女は女王様的な、ムチでバシッてやるっていう、そういうキャラクターをやってくれてるんですけど、そこでムチにしばかれる声が欲しいってことになってね。そしたら千葉さんが、「誰か入って、ちょっと声出して」って、なぜかアフレコの見学に行ってた私が呼ばれて、あの椎名へきるさんに鞭でしばかれる声をやってます(笑)。いま思うとね、そんな馬鹿なことを、本当に真剣に作って…ありがたいですよね。そうそう、みづぼし巽さん[71]と芦田さんが歌ったりね、よくやってるよね。
これ、CDジャーナルのレビューに珍作・珍盤って書いてあって。[72]
そうだよね。これキャスティングを見ると恐ろしいんです。すごい人たちがいっぱい並んでる。井上喜久子さん[73]と山寺宏一さん[74]は夫婦役だからね。
すごいメンバーだ。国府田マリ子さん[75]も出てる。くじらさん[76]も出てるんだね…すごいな。久川綾さん[77]が主役だけど、主役の男の子をやってもらおうってのは確か私が言ったんじゃなかったかな。この前に久川さんの記事をいっぱい私がやってて、男の子の役はあまりやってないって話を聞いてたのかな。それならやってもらいたいよねって、お願いしたんです。ひょっとしたら久川さん、主役の男の子は初めてじゃないかな。
あとはやっぱり貴家堂子さん[78]でしょ、よく来てくれたなよね。あんなよくわからないキャラクター(まいどくん)に…よく考えたら、そのOUTのまいどくん[79]というキャラクターに初めて声がついたんだよね。我々のマスコットキャラに、アニメにはならなかったけどちゃんと声がついて、それが貴家堂子さんだっていうのは、ちょっとOUTとしては誇らしいよね。
それから山本正之さん[80]が作曲してくれて…レコーディングに行きましたよ。この脚本の一人の竹田裕一郎さん[81]って、今いろんなゲームとかアニメの脚本家だからね。OUTのライターしながら、脚本の勉強もされていて。
キャラクター原案の中に向井執菜って投稿者の名前も出ていますね。
そう、だって投稿してるイラストを元に、芦田さんに描いてもらってるから。彼ら・彼女たちはいま何してるんだろうね。
これは後期のOUTらしさの、極地じゃないかなと思います。
そうかな。雑誌以外でシンボルとしてこういう形で残せたってのもよかった。でも覚えてる人って誰がいるんだろうって感じだけど。
この当時雑誌を読んでた人はみんな覚えてると思いますけど。
まだCD持ってるのかな、みんな。
持ってるでしょう、それはもちろん。うちはあります。
手放したらたぶん二度と手に入らないよね。
無理でしょうね。
そんなに売れなかったから、アニメ化の話ももちろんなかったし…。売れたらっていう話はしてるんだよ。もちろん我々的にはそこまで売れないよねって思ってたけど。これ、当時のOUT読者の何パーセントが買ったんだろう…私も枚数は知らないんだ[82]。この時代、OUTの後半から終わりあたり、エヴァのあたり('95年)までなんだけど、アニメ業界にはバブルの残り香があって、バブルって本当は'80年代の後半ぐらいで終わるはずなのに、放送業界もそうだけど日本の社会の流れに対してアニメ界ってちょっとずれて終わっていくので、そこの残り香的な部分ですよ。
そのあたりまでは、そういう遊びが許されていたというか、ファンも乗ってくれた時代。その後はだんだんそういうのができなくなっちゃったから。今の若い子たちが、雑誌からCDを出しましたって聞いてもきっと信じられないよね。読者投稿のキャラクターデザインで、読者が一緒に歌って、CD出しました、なんて。
今はむしろ同人誌とかでやろうと思えばできちゃうっていうのはあると思いますけど、こんな風にちゃんとお金をそれなりにかけて遊ぼうっていうのは…
なかなかないよね。よくやりましたよ。もちろんスタジオ・ライブさんがいてくれたからですけど。声優さんたちもさ、いくら仕事とはいえ、よくやってくれたよ、よく事務所が断らなかったよ。
そこは人間関係ですか。
音響監督の千葉さんからちゃんと仕事が行ってるからだと思います。あと、メーカーが、ソニーさんだから。でも大徳さんの時代に、アウトシャイダーとかザッシギャラン[83]とかああいうのを作って、それを表紙にまでしちゃったOUTがっていうのがあったからじゃないかなと思うんだよな。
そうですね。読者層はもう入れ替わってた頃だと思うんですけど、業界の人がそれは知ってたんじゃないかなって気がします。
それはあるかもしれないね。
でもそのザッシギャランは三条陸だって知ってる人は少ないと思うよ。
それは少ないでしょうね。三条陸さんもぜひお話を伺いたいんです。
ぜひぜひ聞きに行ってください。ザッシギャランの話、聞いてくださいよ。三条陸さんたち、あの世代の人たちはおもちゃも特撮もアニメも大好きで、すごい人たちだったんですよ。あの世代ってテレビ漫画の時代がメインだから、アニメ・漫画・特撮の区別がなくて全部一緒。みんな好きなんだよ。それがOUTも含めたアニメ雑誌ができて、アニメだけを取り上げることによって、特撮と分離しちゃったんだよね。
アニメっていうジャンルが活発になればなるほど、特撮と分かれてしまう。
子供向けの「テレビランド」や「テレビマガジン」ってアニメも特撮も一緒だったでしょ。だから子供にとっては同じカテゴリーなんだよね。でもアニメの専門誌ができて、セル画と特撮の合成は違うとか、撮り方も役者さんも違うってわかってきちゃった。「違うもの」って言った方が詳しそうでかっこいいもん。それもあると思う。OUTが面白かったのは、サブカル誌っていうことでなんでもかんでもやってたから、そこが混ざってるからだったんじゃないかな。特撮のおもちゃもいっぱいやってたよね。
そうですね。須田留貧さんのおもちゃページ[84]も最初はいちばん後ろの方のページでひっそりやってたのが、だんだん前の方に来て、2ページになったりカラーになったりして。
そう、それもそうだし、後に今のTARKUS(タルカス)の社長になった五十嵐浩司くん[85]がアニメのページもずっとやってくれてたんだけど、彼もおもちゃ大好きで詳しくて、もう超合金系とかだったら博士級に詳しい人なの。その人がずっとライターしてた。今は開発の方も手伝っているみたいだし、そういう人がやっぱりOUTにいたんですよ。
それでいうと音楽も、電気グルーヴ[86]のインタビューがあるでしょ。あの時は、やなぎぃがいなかったら成り立ってないからね。あれは確か、彼が今度電気グルーヴの新譜(『KARATEKA』)が出るって話を編集部でしてて「あの人達、OUTの元読者ですよ」って。「じゃあ試しにインタビュー申し込んでみる?」って、あれもソニーだったけど、お願いしたら「いいですよ」って…あの電気グルーヴがOUTに載ってるんだよ。さっき言ったおもちゃもF1もそうだけど、なんでも載せられるんだなってのは、OUTだからかもしれないね。
でも、電気グルーヴもよくOKしてくれたよね。で、インタビューの時にメンバーの一人(石野卓球)が遅刻してきたわけ。「そこまで含めて記事にしていいですか」って聞いたら、「してください」って言われたんで、「もちろん喜んで」って記事にさせてもらった。自分の人生の中でも、まさか電グルに会えるとは思ってないから。やっぱりOUTはサブカル誌なんだね。
(某アニメを取り上げた某号で、表紙で少し無茶をやって怒られた、という話のあと)でも、怒られてなんぼとは言わないけど、そのぐらいやんなきゃダメでしょ。しょせん雑誌なので。休刊号だって馬鹿やってるしね。
95年5月号「世界最速スクープ!ラムネス07」:当時TVシリーズ・OVAとも終了していたラムネが復活し、新作の劇場作品として公開される、というカラー記事。オープニングと称したCGがすでに『マクロス7』のパロディ。最後のページの吹き出しに「SHINJI TENJA NEYO!」とか「だって嘘だも〜ん」と書いている。
もう明快に嘘だってわかるように書いてるけど、よく見たらイラストとかぜんぶ描き起こしだからね。伊東岳彦さんとか、みんなすごい人たちにお願いして、セルまで作ってもらって。このCGは、『ヤマト』とか『ガンダム』のモニターとかのデザインをやってる佐山義則さん[87]がやってくれてるね。
普通にお願いしたらデザイン料とか大変だよ。みなさん「最後ならいいよ、やってやるよ」って、ほぼほぼ安い値段でやってくれた。
ここに「嘘です」って書いてありますね。
書かないと良くない。なぜかというと、『ラムネ&40』のムック本の1冊目[88]は、最後にOVAの1本目のボツ脚本を新作っぽく載せて「こんなのを予定してます」って書いて、最後に嘘っていうか、違うよって本文中に書いたんだけど。そしたら、とある雑誌の奥付けページの上に新作情報がちょっと載るんだけど、そこに「ラムネ&40に新作の話があって、こんなのが出るらしい」って、そのムックに私が嘘だって書いたのが載っちゃった。
ひとこと聞いてくれれば答えるんだよ、嘘ですよって。それか『ラムネ&40』なんだから葦プロとかキングレコードに言えばわかるのに、聞かずに書いちゃったのかな。で、やばい、こういうのはちゃんと分かるように書かなきゃいけないって。だから冗談が冗談じゃなくなっちゃう時があるわけです。

これの前にも冗談企画が時々あるんですけど、昔は小さくしか書いてなかったものが、その頃になるとけっこう大きく「嘘です」ってはっきり書いてるんですよ。
時代が変わってきて、OUTは冗談が載る本だと思ってくれてない世代が増えたんだろうね。たぶんみなさんは読んでて「こいつらまたやりやがって」とか思うわけでしょ。でもそうじゃない世代が読み始めてる時代だったんじゃないかな。あと、さっき言った、OUTに慣れてない業界人がいて、単純な情報を見てあれっと思う人が増えちゃったんだろうね。
投稿ページ(お茶の水研究所)で、イラストの木野さんと構成のMさんの役割を交替しなさいっていうネタ[89]があって。
へえ、そんなのあったっけ?
それでMさんがイラストを描いて、木野さんが投稿の選者をしている回があるんですけど、それを投稿したのが、のちに「涼宮ハルヒの憂鬱」[90]を書く、谷川流さんなんですよね。それがすごくおもしろかった。
全然覚えてないな。ていうかさ、谷川流さんはOUTの読者だったんだよね。同じペンネームの投稿者がいたのは覚えてるんだけど、彼はそれを公に自分で書いてるの?
それが、たぶんないと思うんですよね。
だから、『ハルヒ』がアニメ化した時にすごい悩んだの。みんな彼はOUT読者って言ってくれるけど、ペンネームだから自分の中で確定ができないわけよ。
読者の中にプロデビューしてる人が何人もいて、それは知ってるけど、絵も変わっちゃってるからわからない人もいる。で、私は、皆さんのことをハガキで覚えてるんですよ。絵の人は絵を、文字投稿の方はペンネームとか字面を見ないとピンとこないんだよね。そこは申し訳ないと思うけど。
僕らもそうですよ。例えば、「岐阜県 日吉の月吉」[91]みたいな、セットで覚えている。
そうだね。あとはそういう常連の人たちって、ペンなんかもそれぞれ違うんだ。それは印象に残ってる。一時期まで、OUTが終わった瞬間のハガキはうちに取ってたんだよ。常連のハガキの枚数が多い人には返せるなと思って。でもさすがにずっとはとっておけないんで、ちゃんと処分しましたけど。
あの頃はさ、投稿者のハガキの採用したぶんは普通に編集部にあったわけですよ。没は早めに処分しちゃうんだけどね。でも最近は個人情報保護法っていうのがあって、読者のプライベートな情報を取っておいてはいけないんだよね。投稿は投稿であって、それをリスト化したりするのはいけないんですよ。だから当然持ち帰れないし、取っておくこともできないので、処分しなくてはいけない。投稿雑誌が難しくなったっていうのはそれもある。
なるほどそうですよね。普通の企業でも顧客情報の保持はちゃんと許諾を得なきゃってなりますから。
大徳さんのインタビューにもあったよね。OUTみたいなのをもう1回お願いしますって言われたって。私も何回か言われたけど、無理ですよ。それは個人情報もそうだし、まさにSNSがある時代にやる意味あるんですかと。我々としては理屈はちゃんとあるんだよ。もしやるとしたらこうしなきゃいけない、とか。
皆さんは少しは感じると思うけど、SNSのダメなとこってさ、10人投稿して10人載るでしょ。全部が見てもらえるっていうフリーダムはあるけど、雑誌って編集者だったりコーナー担当がいてその人のフィルターを通ってるから、レベルが一つ上がるんだよね。あと、流れ…順番があるじゃない。ランダムじゃないからそこに意味があったり、この次はこれ、ここでコメント挟んで、っていう流れを意図的に作ってるわけ。その違いはあるけど、でもそれが本として売れますかって言うと、無理でしょう。
だったらもう限定して、漫画投稿とか1発ネタ、1枚のハガキで…今はハガキじゃないかもしれないけど、1コマの中で完結する1コマネタの特集ページみたいのを作った方がいいでしょってなるわけ。
僕らもだんだんインターネットがそういう風になってきた時に、やっぱり没がないシステムはダメだねって言ってました。
結果的にはそういうことだよね。もちろん没ばっかりの人にとっては、みんなに見てもらえるだけで嬉しいだろうし、それも大事だと思うけど、そうじゃない。
自分はのちにラジオの構成作家をやらせてもらってるけど、いちばん嫌だと思ってるのはそれだね。ハガキって自分の字の大きさによって文字数が決まるでしょ。このスペースしか書けないからって、自分の脳内で反芻して、無駄なネタを削ぎ落としていく。それで書くから短い文章がまとまる。だけどメールだとダーッて書けるから、その投稿者にとってもまとまってない。ネタとしては面白いのにつまらなくなる。だったらXとか、文字数の制限がある中で投稿した方がいいと私は思ってる。
あと、選ぶ時にボツと採用を分けられるのもいいんだよね。SNSって分けられないから、面白みがない。今週はこれだけ(ハガキが)来ましたって山になる。この、嬉しさ・ありがたさ。生で感じると違いますよ。人気もわかるし、そうすると、もっと頑張ろうとか、今度はこういう風にしようとか、やる側もそれはリアルに感じるもんね。
投稿のコーナーで新しいコーナーを作ってなかなか定着しなかったり、それが少しずつ人気が上がったり、別のアイデアのコーナーを作ったらこんなにハガキが来た、みたいな。
もちろんありますよね。これは別に比べてるわけじゃないけど、Nさんがやってたサンライズ系のコーナー[92]があるじゃない。アニメの投稿イラストがいっぱい載ってるコーナーと、私がやってた『ラムネ&40』とかの、ちょっと変化球が好きなコーナーと、どっちが良い悪いじゃなくて、そういう違いもOUTの中であるってのが面白かったなと思うし。Nさんはどっちかというとストレートだったよね。それはそれでもちろん正しいし、そっちの方が多分メジャーで、たぶん若い子たちにとってはベストなんですよ。だってかっこよく描いたり、好きを思い切りぶつけたら載るんだもん。
OUTが終わって、あるところの雑誌のページで投稿をどうしようかっていうことがあった。メールが一般的になった頃かな。もうイラスト投稿はハガキじゃなくてもいい、メールで添付してもいいんじゃないの、と提案したんだよね。例えばJPEGで何MBまでとか何ピクセル×何ピクセルの中でやってくださいとかっていうのを決めればいいんですよって話したけど、まだあの頃はなかなかそれが通じなくてね。担当の人に「そこまで書くとわかんないでしょ」って言われて。
アナログはハガキというサイズがあるからいいんだけど、デジタルだとどんな形でも投稿できちゃう。問題は画角・サイズ感なんだよね。それを決めないと、正方形で描きたいやつとか、縦長で描きたいやつとか出ちゃうから、そういう意味での形は決めなきゃ。それはハガキサイズみたいなのを基準に作ればいいんですよ…って話を何か所かに言ったけど、最初はどこもわかってくれなくて。
結局は自分もそういう雑誌からも離れたりしたから最近のことはよくわからないけど、今はたぶんそれやってると思う。今はもっとデジタルネイティブだから、中学生ぐらいからそういう規定もわかるだろうね。
まさに今、そういう人も多いんじゃないですかね。わざわざ紙で描いてスキャンなんてしないし。
だっていま、下手するとスキャンできないでしょ。昔のスラットスキャナ、普通に売ってないもん。
アルバイトで入って、いちばん初めに飲み会に行ったのって、GさんとNさんで、Lさんもいたかな。その数ヶ月後に今度は大徳さん込みで飲み会があったの。だけどその時はわけわからない、元編集長って何?って。その時は大徳さん時代のOUTをほぼ読んでなくて、どういう人か人柄も読み込んでないから、とても謎だったのを覚えている(笑)。
大徳さんとは、その後も何回か会ったり飲んだりしてるけど、この前のインタビューみたいな話はしないからさ。30年越しにわかったよ。ああ、こういう人だったんだって。私の好きな『ガンダムセンチュリー』はこうできたんだって部分もあって、なるほどなって。
大徳さんと一緒に本を作ったことがない、そこはOUTの後半にしかいなかった自分としては少し負い目だよね。「OUTのこと知っているんですよね」っていう、自分の関わった時期より前から読者だった人達の期待値をちょっとは感じつつも、それがわからない自分がいるっていう意味で。
でもその時代に読んでいた人たちには絶対それがあると思うよ。あの時代のテイストがどこか出てくるとか。私も入ったばっかりの頃は、OUTなんですって言って「ああ、あのOUTの」って出てくるワードはだいたいその時代なの。まあその時代がいちばん長いから当たり前なんだけど。だから私も知らない時代のことを言われると、「わからないんですよね」っていうのも失礼だから、「すいません、僕は最後の方のアニメ誌になっちゃったころなんですよ」っていつも言ってた。それでたまに「小林さんがやっていた時代の読者なんですよ」って言われると、ああよかったって。
あの大徳さんのインタビューで出てきたようなOUTの雰囲気、その残り香があるのは、たぶんGさんだよね。いま振り返るとなるほどなって思うし、だからGさんがいて、Nさんがいてくれたから、私は両方が見えたんだなって思う。だから、あの2人ともっと続けたかったな。
Nさんと2人になった時に、それが嫌だとかそういうんじゃなくて…2人ともアニメ好きでアニメの記事をメインで書いてるから、それはそれでいいんだけど、幅が狭くなった気は今もする。編集者の方向性が似ちゃったっていう段階で、雑誌の中核として持っていたバラエティ感、それはもしかしたら減ったかもしれない。そこは読者側が見るものだから、自分から言っちゃいけないのかもしれないけど。
僕はその当時、編集部もわざとこういう方向性にしたのねって思ってたんですけど、今の歳になって思うと、そういう方向に意図的に持っていったというよりも、そういう人が残って、その個性で好き勝手にやったらああなったんだなと。
その通り、そういう感じがしますね。
(→ その3につづく)[53] 和田慎二 : 漫画家。代表作に『スケバン刑事』『怪盗アマリリス』『ピグマリオ』など。'91年10月号に「ピグマリオ」と「スケバン刑事」アニメ化についての記事が掲載されている。
[54] scrap voiceのゲストのページ : 91年10月号より始まる、ゲストの漫画家が1ページ、身辺雑記などを描くコーナー。「えっ、この人が!」という意外な漫画家も多く登場する。「実はOUTに投稿していた」とカミングアウトする漫画家もちらほら。
[55] 吾妻ひでお : 漫画家。初期のOUTでは'78年8月号特集『吾妻ひでおのメロウな世界』などで取り上げているが、'94年3月号より『吾妻ひでおのマンスリー・ギャラリー』という吾妻キャラクターを紹介する連載が始まり、読者を驚かせた。
[56] 超人ロック : 聖悠紀による漫画作品。'67年から50年以上にわたって掲載誌を転々としながら描き継がれた。OUTで'77年12月号にて特集されるが、それ以前は同人誌と貸本向けの単行本での発表であった。初の商業誌連載は'78年、OUT別冊『ランデヴー』にて。その後、'91年9月号よりOUTにて「聖者の涙」編を連載。
[57] ニュータイプ : 角川書店(のちKADOKAWA)から出版されたアニメ雑誌。創刊は'85年3月。
[58] アニメディア : 学習研究社から発行されたアニメーション雑誌。'81年6月号に創刊。事業取得により2020年以降イードから発行される。
[59] 首藤真司 : 投稿常連。独特のタッチのイラストとパロディのセンス、また色糸で絵を描く「糸絵」で有名。
[60] アウシタン : 月刊OUT読者のこと。女性はアウシターナと呼ばれた。
[61] NG騎士ラムネ&40 : 90年-'91年に放映された葦プロダクション制作のロボットアニメ。キャラクターデザイン原案は伊東岳彦、メカニックデザインは中原れい。
[62] F-1 FREAKS 92 : 「この特集はハッキリ言って編集部の趣味です。」と書かれている。
[63] セナ、マンセル : いずれもレーシング・ドライバー。アイルトン・セナはブラジル出身で'88・'90・'91年とF1ワールドチャンピオンを獲得。'94年にレース中の事故で逝去。ナイジェル・マンセルはイングランド出身、'92年にワールドチャンピオン。
[64] 藤臣柊子 : 漫画家、エッセイスト。少女漫画家として活動していたが、現在はエッセイ漫画を中心に執筆している。
[65] たけばしんご : F1漫画のほか、'93年7月号よりscrap voiceにて『鈴鹿deたこやき』のタイトルでモータースポーツについてのイラストエッセイを連載する。
[66] scrap voice : 91年10月より始まる、エッセイを集めたコーナー。徐々に連載陣が増え、最後には10本もの連載が掲載された。山本正之や京本政樹のほか多数の声優が執筆し、椎名へきるの手描きエッセイはほとんどカオスであった。
[67] F1の取材 : 93年1月号「1ヶ月遅れの日本GPレポート 鈴鹿はやっぱり走れない!」
[68] 千葉繁 : 声優、俳優、音響監督。『うる星やつら』のメガネ役、『北斗の拳』のやられ役やナレーションなどで有名。押井守作品に数多く出演していることでも知られ、『機動警察パトレイバー』のシバシゲオのモデルでもある。
[69] イベントの記事 : 95年1月号「流星皇子TOMMYイベントレポート。また'94年10月号には読者が歌っている写真が載っている。
[70] 椎名へきる : 声優、歌手。'94年『魔法騎士レイアース』獅堂光役など。歌手デビューも'94年。'94年9月号ではOUTの歴史で唯一、声優として表紙を飾っている。
[71] みづぼし巽 : 漫画家、常連投稿者。アニパロ、オリジナル漫画など多くの作品をOUTに寄せながら、投稿コーナーにも投稿していた。『スタジオ・ライブのライブDEずっぽ〜ん!』では芦田豊雄によるみづぼし巽のインタビューが掲載されている('92年10月号)。
[72] CDジャーナルのレビュー : 「92年の月刊OUTの企画が日の目をみた珍作。チープなテーマに込められた、非常に密度の高いマニアックな音楽とドラマ! これは異常だ。奥多摩にこだわるフェティッシュな展開も変なら、百人を越す合唱団もジャケも異常。珍盤マニアはこれを買いのがすな!」
[73] 井上喜久子 : 声優、歌手。'89年より『らんま1/2』天道かすみ役、'90年より『ふしぎの海のナディア』エレクトラ役、'93年より『ああっ 女神さまっ』にてベルダンディー役、など。17歳(おいおい!)
[74] 山寺宏一 : 声優、俳優。ジャンルを問わず様々な作品に出演し、幅広い役をこなすことから「七色の声を持つ男」と呼ばれる。
[75] 国府田マリ子 : 声優、歌手、女優。'93年より『GS美神』のおキヌ役、'94年より『ママレード・ボーイ』の小石川光希役など。
[76] くじら : 声優。おばさん役や、妖怪や異形のキャラクターに定評がある。
[77] 久川綾 : 声優、歌手。'92年より『美少女戦士セーラームーン』にてセーラーマーキュリー役、'93年より『ああっ 女神さまっ』にてスクルド役。
[78] 貴家堂子(さすがたかこ) : 声優。『サザエさん』タラちゃん役、『ハクション大魔王』のアクビ役などが有名。2023年逝去。
[79] まいどくん : 公募で選ばれた、月刊OUTのアイキャッチャー・デザイン。「OUT以外では絶対に選ばれないであろう超オリジナリティ。頭の上の虹模様のパッパラパー感が爆笑を誘い、OUTにぴったりのイメージ」('84年5月号)。「まいどくん」の命名は投稿常連の戸田圭佑('84年8月号)。
[80] 山本正之 : 歌手・シンガーソングライター。『タイムボカンシリーズ』や『J9シリーズ』の主題歌などで有名。OUTではエッセイ『月刊山本朝廷』を'92年10月号より連載。
[81] 竹田裕一郎 : 脚本家。芦田豊雄の誘いにより『新・超幕末少年世紀タカマル 』にて脚本家デビュー。代表作に『勇者王ガオガイガー』など。OUTではスタジオ・ライブのコーナーの構成などを行っていた。
[82] 枚数 : 95年2月号編集後記に「発売から1ヶ月。なんと再プレスも決まりまして、マイナーなりに売れている『TOMMY』です」との記載がある。
[83] アウトシャイダー・ザッシギャラン : 85年5月号より登場するパロディ企画『宇宙編集者アウトシャイダー』のキャラクター。大徳編集長(当時)が扮するアウトシャイダーが、須田留貧(後の三条陸)が扮する悪のザッシギャランと戦うという内容。'86年3月号ではついにアウトシャイダーが表紙を飾るという暴挙に。
[84] 須田留貧の天下無敵のHOBBY : もとは各社からもらう読者へのプレゼント品から特集をする、ということから始まった、おもちゃ紹介コーナー。'87年より始まる前身コーナーも含め連載は80回に渡る。
[85] 五十嵐浩司 : 編集者、アニメ研究家。アニメ・特撮・超合金などに関する著書多数。
[86] 電気グルーヴ : テクノ・エレクトロバンド。『電気グルーヴのオールナイトニッポン』での過激な笑いは当時の若者世代に大きな影響を与えた。インタビューは'93年3月号。この時のメンバーは石野卓球・ピエール瀧・まりん。卓球がOUTに投稿して掲載された話や、OUTのレコード紹介を見てレコードを買った話などが載っている。
[87] 佐山義則 : メカニックデザイナー。『宇宙戦艦ヤマト2199』(ディスプレイデザイン)、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』(ディスプレイデザイン)、『機動戦士ガンダムNT』(モニターデザイン)などを手がける。
[88] ラムネ&40 増刊 : ’91年6月増刊『ラムネ&40 熱血必勝攻略本』。同作品ではのちに'92年3月号増刊『ラムネ&40 熱血必勝英雄伝異聞』がある。
[89] お茶の水研究所のネタ : 93年10月号、お茶の水研究所「たまにはお茶研を担当・木野聖子、イラスト・Mでやってもらいたい。いや、なんとなく。兵庫県 谷川流」
[90] 涼宮ハルヒの憂鬱 : 角川スニーカー文庫から刊行されているライトノベル。随所にSFファンがニヤリとするネタが散りばめられている。シリーズ累計部数は2017年時点で2000万部。アニメ版第一期は2006年、新シリーズは2009年。
[91] 日吉の月吉 : 投稿常連。特に『投稿時代』のコーナーにおいて、独特のセンスのイラストで誌面を席巻した。
[92] やったねサンライズ : サンライズ作品についての投稿コーナー。’88年5月号から’94年4月号まで。担当はN。

